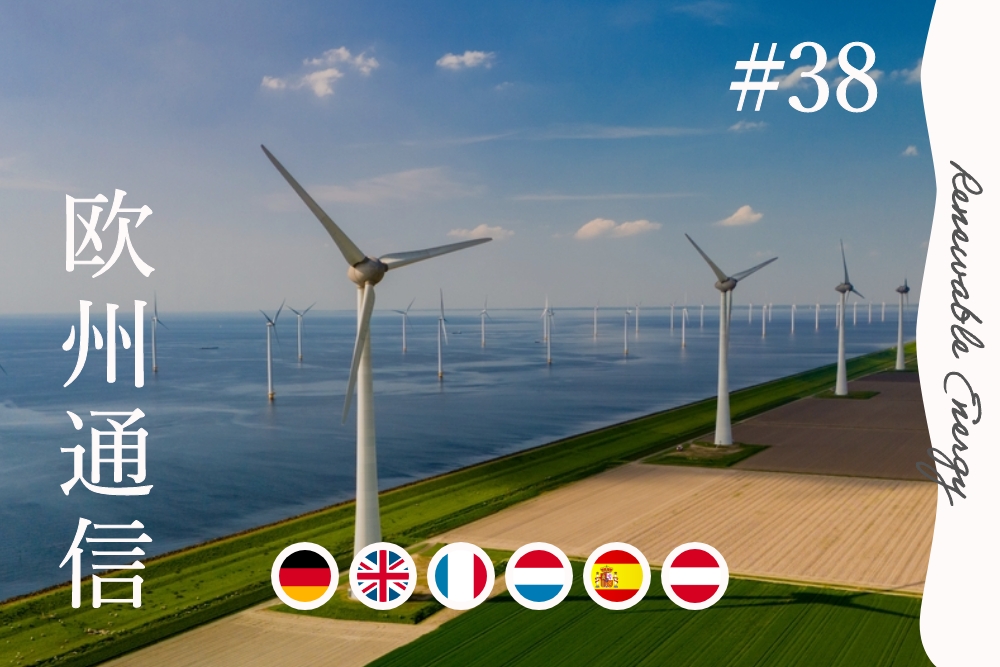近年ヨーロッパは、行政およびビジネスの分野で「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」の実践を目指し、さまざまなユニークな取り組みを生み出してきた。「ハーチ欧州」はそんな欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、日本で暮らす皆さんとともにこれからのサステナビリティの可能性について模索することを目的として活動する。
ハーチ欧州メンバーによる「欧州通信」では、メンバーが欧州の食やファッション、まちづくりなどのさまざまなテーマについてサステナビリティの視点からお届け。現地で話題になっているトピックや、住んでいるからこそわかる現地のリアルを発信していく。
前回は「欧州の最新モビリティ」をテーマに、欧州各都市で見かけるマイクロモビリティの変化を紹介した。今回の欧州通信では「修理」をテーマに、欧州各都市のリペア事情を取り上げていく。
【フランス】パリ市民の暮らしを支える家電のお医者さん「Envie Le Labo」
パリ20区に位置する「Envie Le Labo」は、サーキュラーエコノミーを推進する拠点であり、市民が家電の修理を学び、持続可能な生活を実践できる施設である。壊れた家電をすぐに買い替えるのではなく、修理して使い続ける文化を根付かせることを目的としている。

Photo by Erika Tomiyama
施設では、住民が自宅で壊れた小型家電を持ち込み、専門スタッフから修理サービスを受けることが可能。修理可能な小型家電には、掃除機、調理家電、オーディオ機器などが含まれる。
また、中古家電を低価格で販売している。これらの製品は、パリ郊外にあるリサイクル工場でリファービッシュ(再生・修理)されたもので、単なる中古品ではなく、動作確認や必要な修理を施した上で最低2年間の保証が付いている点が特徴だ。さらに、廃材を活用したDIYワークショップやガイドツアーを開催しており、すべて無料で参加可能であるのも嬉しい。
フランスでは2022年から冷蔵庫や洗濯機などの家庭用電化製品の修理補助金制度(修理ボーナス)が導入され、2023年11月には洋服や靴も補助対象となった。これにより、衣類の修理件数はこの1年間で約3倍に増加し、約82万件の修理が行われたと報告されている。さらに、多くの認定修理業者がこの動きに対応し、売上高が20〜30%増加したというデータもある。
Envie Le Laboは、こうしたフランス全体の修理文化の拡大とも連動し、市民にとっての「家電のお医者さん」としての役割を果たしているのだ。
【オランダ】「修理は新しいクール」市民と企業をつなぐ、アムステルダム発のリペアハブ・United Repair Centre
「修理は新しいクール(Repair is the new cool)」。このスローガンを掲げる「ユナイテッド・リペア・センター(URC)」は、アムステルダムの街角から、衣類リペアを新たなカルチャーにすることを目論む。2022年の設立以来、アウトドアブランド・パタゴニアをはじめ、Decathlonやlululemonなど複数のグローバル企業と提携。住民が愛着を持つ衣類を再生し、年間2万件の修理を手掛けるまでに成長した。

Photo by Kozue Nishizaki
さらにURCは、社会的包摂を実現する就労プラットフォームとしてのもう一つの顔を持つ。従業員の多くは難民や移民など就労機会の少ない人々であり、彼らの持つ裁縫技術を活かせる雇用機会を生み出しているのだ。例えば、20歳のファッション好きのパレスチナ人青年・アンブローズは、URCで働きながらデザインの勉強を続ける。単なる「労働力」ではなく、それぞれの背景やスキルが活かされる職場を提供することが可能だ。
URCに依頼した服が修理を終えて戻ってくることで、消費者自身が「持続可能な選択」を実感できる機会が増える。これは、アムステルダム市が掲げる「2050年までにゼロウェイスト」という目標と連動し、住民一人ひとりがものを長く大切に使うという新たな価値観に触れる機会を生み出すことにもつながる。修理の依頼は、ブランド経由でも個人からでも可能で、受付から返却までのプロセスはシンプルかつスムーズ。最近では、ロンドンにも新拠点を開設し、国境を越えたムーブメントへと広がりつつある。
URCは、単に服を修理する場所ではない。環境問題への意識変革を促し、市民、企業、そして都市全体を巻き込みながら、「修理が当たり前の選択肢」となる社会を目指しているのだ。
【参照サイト】Amsterdam Economic Board – Green Deal Circular Textiles
【イギリス】ロンドン発の衣類修理サービス「SOJO」が、大手小売や百貨店と提携
SOJOは、ロンドン発の衣類修理・リメイクサービスで、地元の仕立て屋とユーザーをつなぐプラットフォーム。アプリを通じて修理内容を選択し、配達員が衣類を受け取り、修理後に届ける仕組みになっている。
2024年8月には、イギリスの大手小売Marks & Spencerとのコラボを発表。「M&S Fixed by SOJO」というオンライン修理サービスを開始した。これにより、M&Sの顧客はオンラインフォームを通じて、ジッパーの交換やニットウェアの修繕など、さまざまな修理サービスを予約できるようになった。修理価格は5ポンド(約950円)からで、衣類はSOJOのチームによって修理され、7~10日以内に顧客の元に返送される。
この投稿をInstagramで見る
さらにイギリスの百貨店・Selfridgesとの提携では、SOJOはロンドンのオックスフォードストリートにあるSelfridges店内に常設の修理スペースを設けている。顧客は店内のこのスペースに衣類を持ち込み、修理やリメイクの相談や依頼が可能だ。衣類はSOJOの専門家によって修理され、完了後に受け取りや配送が行われる。
こうしたコラボを通じて、SOJOはロンドンを中心に多くの市民にとって修理を身近な存在にしている。
【参照サイト】SOJO | Door-To-Door Clothing Alterations and Repairs
【オーストリア】質の高い修理業者が集まる「修理ネットワークウィーン」
「Repair Network Vienna(修理ネットワークウィーン)」は、製品の修理を促進し、「使い捨て文化」に代わる選択肢を提供することを目的に1999年に設立された修理業者のプラットフォームである。設立以来、着実にネットワークを拡大し、質の高い修理サービスを提供し続けている。
修理ネットワークウィーンは自治体の支援を受けて運営されており、現在、150以上の修理業者が登録している。ウィーン市民はサイトから修理業者を見つけることが可能だ。ネットワークウィーンの利用方法は非常にシンプル。サイト上の検索機能で、修理が必要な製品の種類と、居住区や業者を探したい地域の郵便番号を入力すると、最寄りの修理業者の情報と連絡先が写真付きで表示される。そこから、自分のニーズに合った業者を選択。自治体・連邦政府や企業が提供する修理ボーナス制度とも連携している。
質の高い修理サービスを提供するため、このネットワークに登録する業者には一定の基準が設けられており、誰でも登録できるディレクトリとは異なる。そのため利用者は安心して修理を依頼でき、費用や修理に関する疑問も事前にメールや電話で問い合わせ可能だ。

Image via DIE UJMWELTBERATUNG
ネットワークに参加する修理業者は、年間5万件を超える修理を実施しており、これは年間約750トンの廃棄物削減につながるという。また、持続可能で資源効率の高い経済の実現に向け、修理やリユースの重要性を広く発信。企業向けには定期的な修理サービスや修理ワークショップを実施するなど、修理文化の普及にも積極的に取り組んでいる。さらにパートナー業者との協力で、市内の学校向けにワークショップを開催し、無料の出張修理サービスも提供している。
編集後記
各国の事例で見てきたように、「修理」はサーキュラーエコノミーを推進し、人々がものを大切にする文化を育むうえでも重要視されている。これらの取り組みに共通するのは、単なる修理技術の提供にとどまらず、データの活用や政策支援、企業との連携を通じて「修理をより身近なもの」にしている点だ。特にオランダの事例のように、「修理=クール」という意識が醸成されつつあることは興味深い。
日本でも、リペアカフェの開催などを通じて修理の価値を再認識し、より多くの人が手軽に修理を選べる環境を整える動きが見られるようになった。修理が当たり前になれば、資源の浪費を減らすだけでなく、職人技術の継承や、人々の暮らしをより豊かにすることにもつながるのではないだろうか。
Written by Erika Tomiyama, Kozue Nishizaki, Megumi, Yukari
Presented by ハーチ欧州
ドキュメンタリー映画『リペアカフェ』上映プログラム実施中!
IDEAS FOR GOODでは、モノを大切に使い続ける「修理」という行為に焦点を当てたドキュメンタリー映画『リペアカフェ』の上映プログラムを提供しています。使い捨て文化が広がる現代において、「直して使う」という選択肢を見つめ直すことは、私たちの価値観や行動を変える第一歩になるかもしれません。本作品は、壊れたモノを修理しながら、人と人がつながり、持続可能な社会を実現するためのヒントを探る内容となっています。
本ドキュメンタリーは、社内のサステナビリティ意識を高めたい企業や、コミュニケーション活性化を図りたい組織、地域住民の学びの場を提供したい自治体など、さまざまな場面で上映いただけます。修理を通じて人と社会と地球をつなぎ、新たな気づきを得るきっかけづくりにぜひご活用ください。上映に関する詳細やお問い合わせは、こちらの特設ページから!
ハーチ欧州とは?
ハーチ欧州は、2021年に設立された欧州在住メンバーによる事業組織。イギリス・ロンドン、フランス・パリ、オランダ・アムステルダム、ドイツ・ハイデルベルク、オーストリア・ウィーンを主な拠点としています。ハーチ欧州では、欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、これからのサステナビリティの可能性について模索することを目的としています。また同時に日本の知見を欧州へ発信し、サステナビリティの文脈で、欧州と日本をつなぐ役割を果たしていきます。
ハーチ欧州の事業内容・詳細はこちら:https://harch.jp/company/harch-europe
お問い合わせはこちら:https://harch.jp/contact