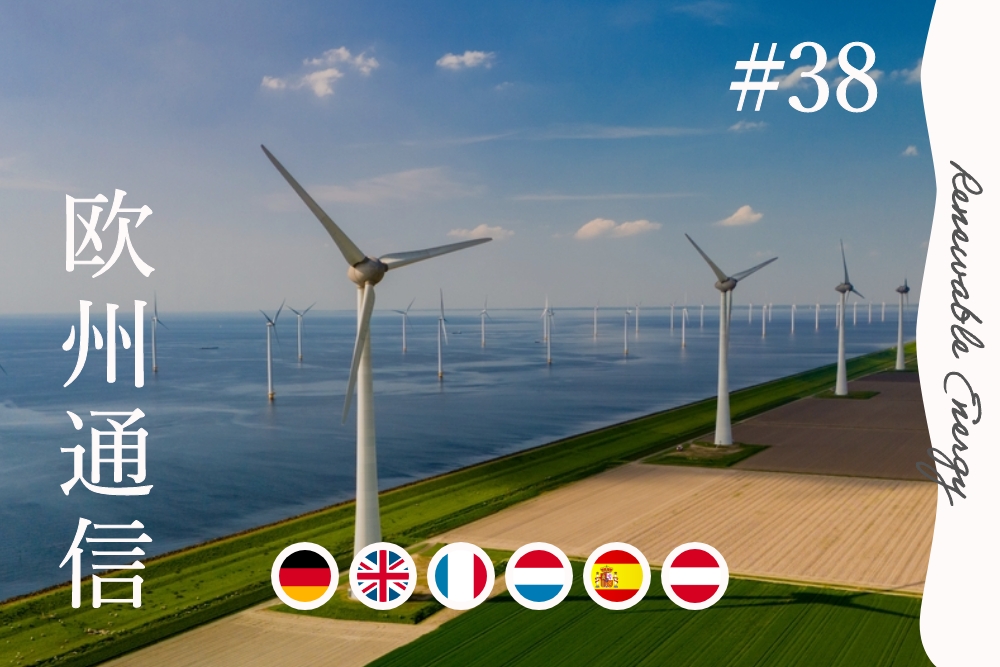近年ヨーロッパは、行政およびビジネスの分野で「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」の実践を目指し、さまざまなユニークな取り組みを生み出してきた。「ハーチ欧州」はそんな欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、日本で暮らす皆さんとともにこれからのサステナビリティの可能性について模索することを目的として活動する。
ハーチ欧州メンバーによる「欧州通信」では、メンバーが欧州の食やファッション、まちづくりなどのさまざまなテーマについてサステナビリティの視点からお届け。現地で話題になっているトピックや、住んでいるからこそわかる現地のリアルを発信していく。
前回は「ネイチャーポジティブ」をテーマに、欧州各都市の制度や取り組みを深掘りした。今回の欧州通信では「働き方」をテーマに、欧州各都市の制度やサステナブルな働き方に関する取り組みをご紹介する。
【イギリス】週4日勤務を本格導入へ。従業員の幸福と生産性を両立、新たな格差も顕在化
2025年1月、イギリスでは、史上最大規模となる「週4日勤務制」の試験導入が実施され、対象企業の約9割が制度の継続を決定し、そのうち4割以上が完全に恒久化した。
週5日分の給与を維持したまま労働時間を20%削減するこの制度は、ストレスの軽減、バーンアウトの抑制、離職率の低下、生活満足度の向上といった多くの効果を生み出した。企業側も生産性の維持や採用競争力の強化といったメリットを実感しており、業種を問わず制度導入が進んでいる。
試験を主導した非営利団体は、「従業員の幸福が企業の利益につながる」という好循環が明らかになったと評価しており、週4日勤務制は一過性ではなく、持続可能な新たな働き方として定着しつつある。
一方で、この新しい制度がすべての労働者に平等な恩恵をもたらしているわけではない。The Guardianの報道によれば、柔軟な働き方の導入は主にオフィスワーカーに集中しており、看護師や小売業従事者など、対面や現場での労働を求められる職種にはほとんど適用されていない。2019年から2024年の間に、柔軟な働き方を享受できるようになった労働者は130万人にのぼるが、その大半はデスクワーカーであり、340万人のシフト労働者にはほとんど変化がなかったという。
こうした実態は、柔軟な働き方の恩恵が一部の労働者に限定されていることを示し、労働市場における新たな二極化を招いている。今後、この制度がどのように拡大・修正されていくのか、その動向を注視する必要があるだろう。
【フランス】フランス発の「つながらない権利」。心の余白を守る、見えない改革
「仕事が終わっても、スマホに届く通知が気になってしまう」。そんな日々に、違和感を覚えたことはないだろうか。テレワークの普及やチャットツールの進化によって、私たちは常に仕事とつながり続けている。その一方で、オンとオフの境目が曖昧になり、気づかぬうちに心の余白が削られてはいないだろうか。
こうした現状にいち早く対応したのがフランスだ。2017年、同国では「つながらない権利(Right to Disconnect)」が法制化された。これは、従業員が勤務時間外に業務連絡に応じない自由を持つことを企業が認め、明文化するよう義務づけたもの。たとえば「夜間や週末のメール送信を控える」「業務用チャットを自動でオフにする」など、具体的な施策が企業によって導入されている。
この制度の背景には、フランス社会に根付く「仕事よりも生活を大切にする」という文化があるように思う。長期のバカンスや家族との夕食の時間を重視する姿勢は、「働くことは人生のすべてではない」という価値観に支えられている。だからこそ、つながらないことは“怠け”ではなく、健やかに働き続けるための知恵として受け入れられている。
そしてこれは、私たちの多くが抱える「なんとなくの疲れ」や「常に追われている感覚」といった、見えないストレスの正体に光を当てる改革でもある。“いつでも働ける”時代にこそ、“いつ休むか”を真剣に考える必要があるのだ。フランスの取り組みは、効率性や生産性だけでは測れない「人間らしい働き方」のヒントを、私たちに投げかけている。
【オランダ】EUで最もパートタイム労働が進む国
オランダは、実はパートタイム労働がEUでもっとも広く浸透している国だ。2023年のデータによれば、同国の女性労働者の約63%がパートタイム勤務をしており、男性においても約23%と、男女ともにEU内で最も高い割合となっている。オランダのパートタイム労働者は単に労働時間が短いだけで、賃金や社会保障、昇進機会などにおいてもフルタイム労働者と同等の待遇が法的に保証されている点が特徴的である。
オランダにおけるパートタイム労働の普及は、1982年のワッセナー協定に端を発する。この協定は、雇用主団体と労働組合との間で締結され、失業率対策として労働時間の短縮やパートタイム雇用の拡大を推進した。この協定によりパートタイム労働が社会的に定着し、1996年にはパートタイム労働者の法的地位がさらに強化されたのだ。賃金や手当、ボーナスなどあらゆる面でフルタイム労働者と同等の待遇が義務づけられたことにより、パートタイム勤務は「不完全な雇用」ではなく、むしろ正規の働き方として位置づけられるようになった。
オランダでは特に子どもを持つ女性の間でパートタイム勤務が一般的で、家庭と仕事の両立を可能にする働き方として広く支持されている。しかし一方で、子どもがいない労働者においてもパートタイム勤務の割合は決して低くない。子どもがいない女性労働者の約30%、男性でも約14%がパートタイム勤務を選んでおり、育児や家庭以外の理由でも短時間勤務が好まれていることを示している。
しかし、こうした働き方に対しては経済的な側面からの批判もある。オランダ銀行(DNB)は、短い労働時間が経済成長や労働市場の逼迫を引き起こしているとして、労働供給の拡大と労働時間延長を推進すべきだと指摘している。政府や企業も柔軟な働き方を維持しながら、育児支援の強化や職場でのフルタイム復帰を促す取り組みを検討しているところである。
オランダの働き方は個人のライフスタイルを尊重し、家庭と仕事のバランスを重視する文化が根付いている。一方、経済の持続的成長のためには、労働時間の見直しを含め、柔軟性と労働供給の拡大を両立させる政策的な対応が求められている。
【参照サイト】Women more likely to have worked part-time in Q3 2023
【参照サイト】Part-time and full-time employment- statistics
【参照サイト】17% of EU workers are part-timers
【参照サイト】Dutch women work part-time even in their 20s with no kids
【参照サイト】The Netherlands has gone part-time. Is it working?
【スペイン】ストレスに編み物、悩みには24時間相談。ユニークなメンタルケア
スペインでは、メンタルヘルス不調による休職者が増加しており、2024年はコロナ前と比べて約72%増と深刻な状況だ。
こうした状況を受け、大手金融機関BBVAでは職員向けの「ウェルビーイングプログラム」を強化。その一つとして、編み物でストレス緩和するというユニークなアプローチを実施している。同社は編み物を「次世代のヨガ」と位置づけており、集中力向上や気分転換、クリエイティビティの刺激に加え、参加者同士のコミュニケーションの活性化にもつなげているのだ。
このようなソフトな取り組みに加え、同社では手堅い支援も実施している。例えば、職員とその家族が匿名で利用できる24時間対応の相談窓口を設置。電話またはオンラインで相談が可能で、導入から半年間で550件以上の相談が寄せられたという。さらに、従業員が自身のメンタルヘルスについて学ぶ機会も提供。提携する医療機関の専門家と連携し、「睡眠衛生の基本」や「感情のマネジメント」などをテーマとした講座を実施しているのだ。
このような包括的な取り組みは、単なる福利厚生にとどまらず、企業としての持続可能性や職員エンゲージメントの向上にも寄与している。スペインでは週37.5時間労働が話題になっているが、今後、官民が連携してメンタルヘルス問題にどう取り組むかが注目されている。
【参照サイト】The impact of wellness initiatives on BBVA’s workforce
編集後記
週4日勤務の恒久化、「つながらない権利」、パートタイム労働の普及、メンタルヘルスへの新しいアプローチ。今、世界全体で生産性や効率といった尺度だけでは測れない「働くことの意味」や「余白の価値」が問い直されている。しかしその一方で、柔軟な働き方を選べるのは一部の人に限られていたり、経済成長とのバランスが課題になったりと、まだまだ理想と現実のギャップも大きいのが現状である。
それでも、確実に進んでいるのは「経済成長を最優先する時代」から、「人と社会の持続可能性を大切にする時代」への価値観のシフトだ。働き方の見直しは、単なる労働条件の改善にとどまらず、気候変動、ジェンダー平等、ケア労働の再評価など、私たちが直面するさまざまな課題とつながっているのである。
日本においても、少子高齢化や人手不足、メンタルヘルスの悪化といった構造的課題が深刻化している。そんな中で、「働くこと」を問い直すことは、もはや単なる福利厚生の話ではない。それは、これからの社会のあり方そのものに直結するテーマなのである。
Written by Megumi, Erika Tomiyama, Kozue Nishizaki, Risa Wakana
Presented by ハーチ欧州
ハーチ欧州とは?
ハーチ欧州は、2021年に設立された欧州在住メンバーによる事業組織。イギリス・ロンドン、フランス・パリ、オランダ・アムステルダム、ドイツ・ハイデルベルク、オーストリア・ウィーンを主な拠点としています。ハーチ欧州では、欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、これからのサステナビリティの可能性について模索することを目的としています。また同時に日本の知見を欧州へ発信し、サステナビリティの文脈で、欧州と日本をつなぐ役割を果たしていきます。
ハーチ欧州の事業内容・詳細はこちら:https://harch.jp/company/harch-europe
お問い合わせはこちら:https://harch.jp/contact