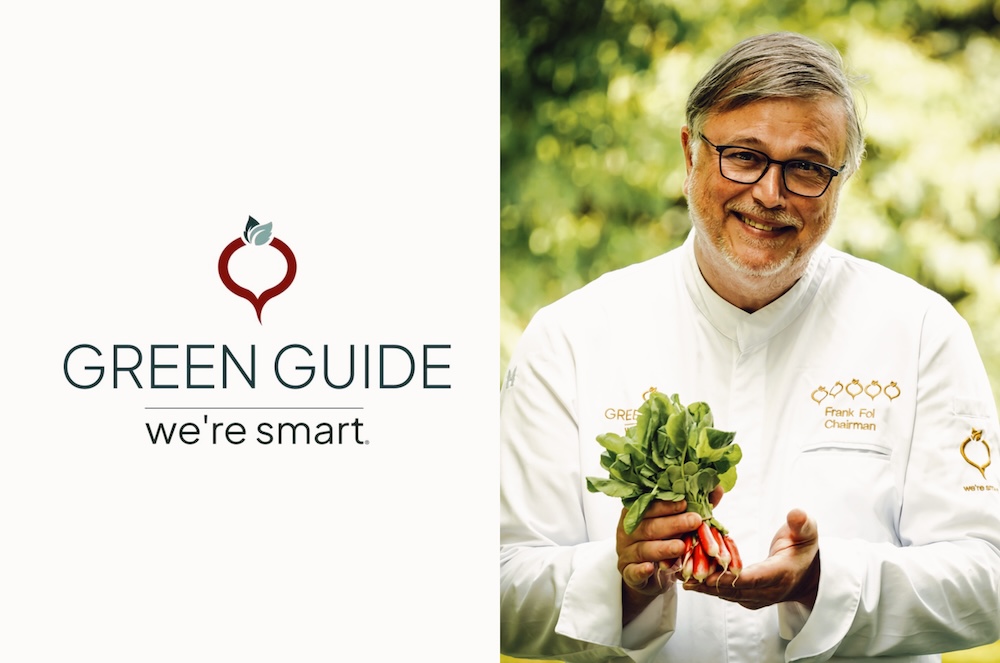「私たちは、ガストロノミーで何を変えられるのか?」
そんな根源的な問いに対し、食というフィールドから確かな熱をもって答えを提示し続けている料理人がいる。東京・紀尾井町のレストラン「MAZ(マス)」でヘッドシェフを務める、サンティアゴ・フェルナンデス氏だ。
ベネズエラ・カラカスに生まれ、美食の地として名高いスペインのバスク・カリナリー・センターで研鑽を積んだ彼が自身の哲学を見出したのは、ペルー・リマの地だった。世界のベストレストラン50で何度も1位に輝くミシュラン三つ星レストラン「Central(セントラル)」との出会いが、彼の運命を大きく動かす。そこで彼は、単なる料理技術ではなく、“土地と自然を深く見つめる思想としてのガストロノミー”に触れたのだ。
弱冠20代で、Centralが設立した研究機関「Mater Iniciativa(マテル・イニシアティバ)」に参加。食材のルーツやその土地固有の文化、生態系への理解を深めながら、料理を通じて社会や環境とつながる実践を重ねていく。
そして2022年7月、その哲学を胸に東京で「MAZ」をオープン。文化や風土の違いを受け入れながら、日本という新たな土地で、サステナビリティの思想をガストロノミーという表現に昇華させている。
「サステナビリティとは、一過性の流行ではありません。文化や土地、人と“共に創っていく”という姿勢そのものです」
そう語る彼の思想に深く共鳴し、“Social Food Gastronomy(ソーシャルフード・ガストロノミー)”を提唱するシェフ・杉浦仁志氏が、食の分野におけるサステナブルな未来を切り拓くキーパーソンを紹介する本連載。
今回は、サンティアゴ・フェルナンデス氏の言葉の真意を探るため、東京での現在の活動を起点に、彼の原点であるペルーの研究機関「Mater Iniciativa」での取り組みまで遡りながら、その思考をひもといていく。

杉浦シェフ(左)とサンティアゴ・フェルナンデス氏(右)
海を越えてたどり着いた、ガストロノミーと哲学の交点
「僕の役割は“料理を作る人”ではなく、“自然を翻訳する人”に近いと思っています」
MAZが掲げるコンセプトは「垂直的視点(Vertical Gaze)」。これは、ペルーのアンデス山脈が持つ、標高差による多様な生態系をひとつの世界観として捉える考え方だ。彼の創り出す料理は、単に美味しいだけでなく、私たち人間が「自然の声に耳を傾けるための言語」なのである。

その哲学を体現するため、MAZではアンデスの生態系に着想を得ながら、日本の「旬」やその土地ならではの風土が育む個性(テロワール)を織り込んだ独創的な料理を展開。コースを構成する食材の約80%が日本産であり、残りの20%をペルーの希少な素材で補っている。
日本各地の生産者と密接に連携し、その土地の個性を深く読み解き、料理という言語で再構築するアプローチは、まさにMAZが奏でるローカルとグローバルの対話と言えるだろう。
“日本の旬”は、垂直性と融合する
サンティアゴ氏は、日本の伝統的な食文化、特に「会席」に深く感銘を受けたと語る。
「会席は、旬の恵みを最大限に活かし、季節の移ろいを繊細に表現する、自然と向き合う素晴らしい哲学です。MAZでは、その日本の“季節”という時間軸の考え方と、ペルーの“標高”という空間軸の考え方を融合させました。これを私たちは『ヴァーティカル会席(垂直の会席)』と呼んでいます」
彼の探究フィールドは、都市部だけに留まらない。2023年には、新潟の「里山十帖」とコラボレーションイベントを実施するなど、積極的に地方へ足を運んでいる。サンティアゴ氏は、日本の地方に眠る食材や風景、そして“声なき価値”を世界へ伝えることに強い意欲を見せる。
「日本の山の幸、例えばジュンサイや山椒、あるいは僕がまだ知らないような素晴らしい食材がたくさんあります。MAZのフィロソフィーを通してそれらを再解釈し、国内外へ発信していくことは、非常に価値のある挑戦だと考えています」

サステナビリティとは、食べ手の感性を育てること
MAZのコースには、ときとして「ジャガイモ1個とソースだけ」という、極めてシンプルな一皿が登場することがある。これは、彼の哲学を映し出す象徴的な一皿だ。
「食材の本当の価値は、その裏側にある労働と知恵に宿る」という力強いメッセージが込められている。
「多くの人はジャガイモよりアスパラガスの方が高級だと考えがちです。しかし、アンデスの厳しい環境で多様なジャガイモを栽培し、収穫する手間は計り知れません。高級とは、希少性や価格のことではない。尊重されるべき手間や物語こそが高級なのだと、意識を転換する必要があります。そこにシェフのクリエイティビティーが加わることで、新たな価値が生まれるのです」
食材の背景にある物語を伝え、食べる側の意識を変革しようとする彼の圧倒的な行動力は、世界中の料理人や美食家から感銘を集めている。
ガストロノミーは、地域社会を変える“エージェント”
MAZの独創的なガストロノミーを根幹で支えているのが、シェフのヴィルヒリオ・マルティネス氏が率いるペルーの研究プロジェクト「Mater Iniciativa」だ。ここは単なるキッチンではなく、多様な専門家が集うリサーチセンター(研究所)である。
「Googleで名前を調べるだけでは、食材の本質は見えてきません。山の上に住むおばあちゃんが持つ、世代を超えて受け継がれてきた知識こそが、未来のヒントになるんです」

Mater Iniciativaの思想を最も色濃く体現しているのが、クスコ郊外の標高3,500メートルを超える高地に構えるリサーチセンター併設レストラン「MIL(ミル)」だ。
インカ時代の知恵を応用し、段々畑(アンデネス)で多様な作物を育てるこの場所は、まさに「天空のラボ」。農学者、料理人、アーティスト、そして地域の先住民たちが集い、在来種のジャガイモやキヌアの研究、伝統的な発酵飲料の開発などが日々行われている。

MIL Centro is a Timeless Journey at 3568 masl.
MILは、アンデス高度3,500メートルを超える厳しい環境に、1.39ヘクタールの農場「Chacra MIL」を地域コミュニティと共同で管理している。そこでは、インカ時代から伝わる暦に基づき、在来種のジャガイモやキヌア、トウモロコシといった多様な作物を実験的に栽培。この活動は単なる農業に留まらず、社会科学、植物学、文化人類学といった多様な専門家が連携する学際的な研究の場となっているのだ。
特筆すべきは、地域コミュニティとの深い共生関係である。MILは、収益の50%を地域コミュニティへ分配するだけでなく、収穫作業や古くから伝わる種子の保存といった知恵も共有し、経済的・文化的な共生を実現している。これは、先住民コミュニティの伝統を搾取するのではなく、対等なパートナーとして共に歩む脱植民地主義的な研究アプローチの実践だろう。
そして、これら食、農、文化を繋ぐ一連の活動は、訪れる人が五感で体験できる「イマージョン(没入)ツアー」として提供され、持続可能なガストロノミーツーリズムという形に結実している。
この「MIL」の活動は、モライのコミュニティに安定した雇用と誇りを生み出し、新たな観光誘致にも繋がっている。サンティアゴ氏は、このモデルを日本の地方が抱える課題解決にも応用できるはずだと、確信しているそうだ。
「かつて、この地域の村々の収入は農作物の出来不出来に大きく左右されていました。しかし今、レストランと研究所があることで、彼らの生活は安定しました。私たちのレストランは、地域社会をより良く変えるための“エージェント(代理人)”でもあるのです」

サステナビリティは“問い”を持ち帰ってもらうこと
サンティアゴ氏にとって、レストランは単に食事を提供する場所ではない。
「お客様に『美味しかった』と感じてもらうだけでは、もう足りないんです。料理を通して、何か一つでも考えたくなるきっかけや問いを持ち帰ってもらいたい。味覚と知覚、その両方を揺さぶること。それこそが、これからのサステナブルなガストロノミーが担うべき役割だと信じています」
MAZで繰り広げられる一皿ひと皿は、ペルーと日本、都市と地方、過去と未来を繋ぐ壮大な物語の一片だ。彼が描く食の哲学は、日本に留まらず、世界の食に関わるすべての人々が学ぶべき未来志向のロールモデルと言えるだろう。
サステナビリティとは、再利用や省資源だけではなく、「私たちの感性を育て直すこと」なのかもしれない。MAZの一皿一皿には、科学、芸術、農業、そして先住民の知恵まで、多様なレイヤーが丁寧に編み込まれている。その複雑な対話に耳を澄ませ、自らの感性で問いを受け取る──その体験こそが、未来のレストランが果たすべき本質的な役割なのではないだろうか。
【参照サイト】Mater – Research Center
【参照サイト】MIL Centro is a Timeless Journey at 3568 masl.
Edited by Erika Tomiyama