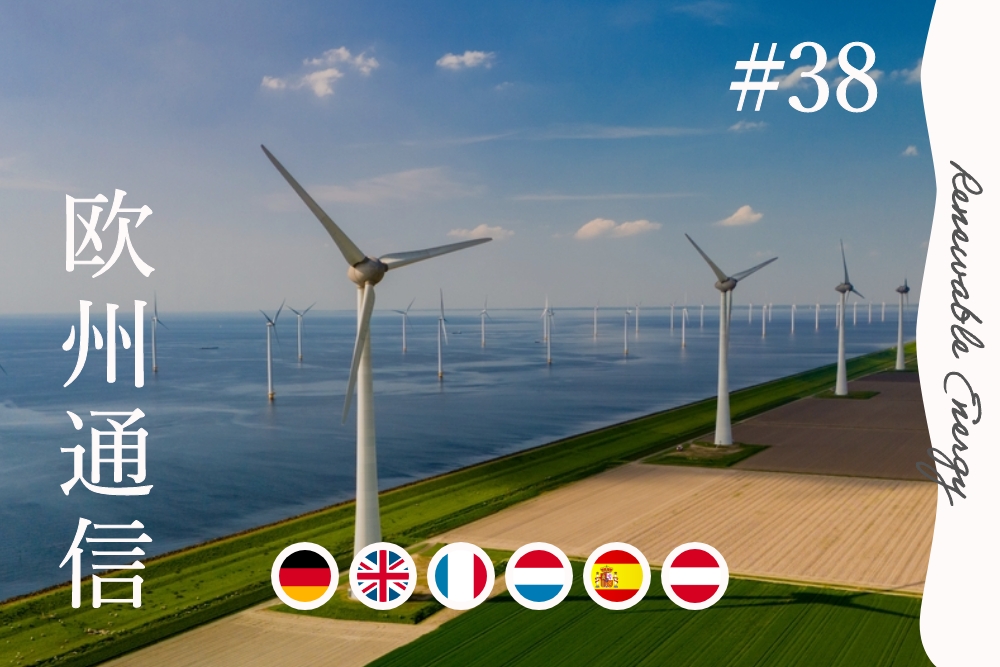日本に先駆けて、ヨーロッパは行政およびビジネスの分野で「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」の実践を目指し、現在に至るまで世界を主導してきた。そんな欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、日本で暮らす皆さんとともにこれからのサステナビリティの可能性について模索することを目的として活動する「ハーチ欧州」。
そんなハーチ欧州メンバーによる「欧州通信」では、メンバーが欧州の食やファッション、まちづくりなどのさまざまなテーマについてサステナビリティの視点からお届けする。現地で話題になっているトピックや、住んでいるからこそわかる現地のリアルを発信していく。
前回は、「ファッション」をテーマに、オーストリアのリサイクル百貨店や、ドイツの「服装の自由」の文化など、新しいものを取り入れるのではなく、「いまここにあるもの」に目を向ける発想の転換を見てきた。第2回目のテーマは「スーパー」。フランス、オーストリア、イギリス、オランダ、ドイツのスーパー最新事情を、現地からお届けする。
【フランス・パリ】「旬の野菜かどうか」ひと目で分かるバロメーター
フランス人の71%が少なくとも月に1回はオーガニック食品を消費しているというデータがあるほど、フランスでは「自分が何を食べているのか」を気にする人が多い。そんなフランスでは、食品パッケージのバーコードをスキャンすると4段階で即座に食品を評価してくれるアプリ「YUKA」が大人気だ。

Photo by Erika Tomiyama
フランスの小規模チェーンスーパー「カジノ」では、果物や野菜が旬のものどうかを知れるバロメーターがある。「季節の始まりたて/終わりかけ」「旬ど真ん中」「季節外れ」の3段階で表されたイラストが用意されており、全店舗で適用されている。こうして買い物客は、旬の栄養価の高い食材を楽しみながら、食糧生産における生産エネルギー削減をすることで環境負荷を抑えることができる仕組みになっているのだ。
【オーストリア・ウィーン】プラスチック包装ゼロを推進する食品店
ウィーンからは、環境保全とSDGsの推進を店の経営方針としている食品店「グライスラー(Greissler)」を紹介する。2015年に設立され、市内に2つの店舗を構えるこの店の哲学は「容器・包装なし・地産・オーガニック・フェアトレード」。店内で販売される食品は、この4項目のうち最低3つを満たしていることが条件だ。特に容器包装に関しては、プラスチック不使用を掲げており、トイレットペーパーやキッチンペーパーの包装も紙袋という徹底ぶりである。

紙の包装をされたトイレットペーパー(左)と近郊の農家から取り寄せられた野菜(右)|Photo by Yukari Fujiwara
野菜はウィーン近郊の農家から直接仕入れており、そうでないものはオーガニックでフェア・トレードの認定を受けた品物のみを扱う。お客さんは基本的に紙袋・布袋・ガラス容器などの容器持参で買いものに来るが、店内で紙袋の購入も可能。ここで販売される商品は、厳しい条件のもとで仕入れているため値段は通常のスーパーで売られているものより割高だ。
商品の価格について店内のお客さんに聞いてみた。「品物の質を考えると決して高いとは思いません。どこから来たのか明確で新鮮です」、毎回の容器・包装の持ち込みについては「もう習慣ですから」という答えが返ってきた。
【イギリス・ロンドン】容器を買う必要なし。地元密着の量り売りショップ
ロンドン北部にあるKiloは2020年にできた量り売りショップ。パスタや穀物、スパイス、ジュースや植物性ミルク、洗剤まで、すべて量り売りで買うことができる。ヨーロッパで量り売りのお店自体は見かけることも多くなったが、Kiloの特徴は専用のアプリと商品についているバーコードを使って、お客さんがスマートフォン上で会計までできることだ。すべてが画面上で完結するため、頻繁に店を訪れる人にとっては嬉しいシステムだ。

Photo by Megumi
また、商品を入れるための瓶などを持参しなかったとしても、容器は近隣の人から寄付されたものを無料で使うことができる。(容器はすべて店舗で洗浄・消毒済み。)「ふらっと立ち寄ったゼロウェイストショップで結局容器を買うことになってしまう」というジレンマを、店舗と近隣と人々のつながりが解決してくれる。お店のゼロウェイストポリシーに則り、レシートがメールで届くのも特徴だ。

Photo by Megumi
【オランダ・アムステルダム】欧州イチ「肉食離れ」がすすむオランダのヴィーガン事情
オランダ中央統計局が2020年に行った調査によると、オランダ人の80%が「肉を毎日は食べない」、45%は「肉は週に4回かそれ以下しか食べない」と回答。3分の1は、前年と比べ肉を食べることが減ったと回答するなど、オランダ人の「肉食離れ」が進んでいることが明らかになった。
これはオランダが進めるサーキュラーエコノミー戦略と大きく関連している。環境負荷を減らすためにオランダは2030年までに肉の消費を50%削減する目標を掲げたのだ。2020年の年間1人あたり平均45.3キロから、23.1キロにまで肉の消費を減少させなければいけないことになる。
人々の健康を保ちながらこの目標を達成するために、オランダは動物性タンパク質から植物性タンパク質への移行を進めている。過去2年間で植物性素材からなる代替肉食品と乳製品代替食品の消費が50%増加。市場は2億9,100万ユーロ(日本円約381億円)へと拡大した。

写真に収められているのは、すべて「肉ではない代替肉」食品だ。|Photo by Kozue Nishizaki
オランダでは、どのスーパーでも手軽に安価で代替肉を手に入れることができる。代替肉食品には通常の生鮮肉売り場の半分ほどのサイズで大きな棚が充てられ、ひき肉やハンバーグ、鶏ささみ、チキンナゲットなどを模した豊富な種類の商品が並ぶ。また、これとは別にハムなどの加工肉売り場にも、ミルクやチーズなどの乳製品売り場にも、必ず植物性の代替食品が設置されている。値段は実際の肉・乳製品と同様か少し高い程度と、手軽に購入することができるのも特徴だ。おすすめはBeyond Burger。ジューシーで、レタスやトマトと共にバンズに挟んで食べるとまさに肉そのものだ。

Photo by Kozue Nishizaki
【ドイツ・ハイデルベルク】スーパーでのちょっとした会話が、地域社会のウェルビーイング向上に
ドイツのスーパーでは会計のとき、多くの店員がお客さんの顔を見て「こんにちは」と声を掛け、会計が終わると、またお客さんの顔を見て「いい一日を」と声を掛ける。お客さんも「こんにちは」「ありがとう。あなたもいい一日を」と返答する。大手スーパーでも顔なじみになってくると、挨拶に加えて雑談することもある。

Photo by クリューガー量子
1週間に何度か行くスーパーでは、誰もが店員さんと顔を合わせる。店員さんがしっかりお客さんの顔を見て挨拶をしてくれることは、「また、あのスーパーで買物をしたい」という気持ちにつながり、スーパーとしても重要なサービスの一つとなる。特に、一人暮らしの高齢者などは、店員さんとの会話が一日の唯一の会話という人も少なくない。スーパーでの小さな会話は、こうした高齢者などの生活の質向上につながるはずだ。
筆者がよく行く大手スーパーには、地元で有名な人気の男性店員さんがいる。いつも笑顔で子供にもよく話しかけ、そのお客さんにあった話をしてくれる。筆者にはいつも「いらっしゃいませ。久しぶりですね。元気ですか?」などと日本語で話しかけてくれるので、彼のレジの列が他のレジより少し長くても、彼のレジに並びたくなってしまう。
編集後記
品質の高いものを環境負荷の低い方法で販売することが重要視されている昨今。ヨーロッパ各国で、消費者に「どのように商品のことを説明するか」「どのような買いもの体験をしてもらうか」ということに関する工夫が目立った。デリバリーのサービスも増えている中で、店舗での買いものに関しては、どうせなら楽しく、快適になるような「コミュニケーション」が鍵になってくるのかもしれない。
「欧州通信」はIDEAS FOR GOODのインスタグラムでも、随時更新しています。ヨーロッパのサステナブル事情に興味のある方は、ぜひフォローしてみてください。
ハーチ欧州とは?
ハーチ欧州は、2021年に設立された欧州在住メンバーによる事業組織。イギリス・ロンドン、フランス・パリ、オランダ・アムステルダム、ドイツ・ハイデルベルク、オーストリア・ウィーンを主な拠点としています。ハーチ欧州では、欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、これからのサステナビリティの可能性について模索することを目的としています。また同時に日本の知見を欧州へ発信し、サステナビリティの文脈で、欧州と日本をつなぐ役割を果たしていきます。
事業内容・詳細はこちら:https://harch.jp/company/harch-europe
▶ぜひハーチ欧州お問い合わせページからお気軽にお問合せください。
【関連記事】フランスのスーパーに導入された「旬の野菜かどうか」を知れるバロメーター