特集「多元世界をめぐる(Discover the Pluriverse)」
私たちは、無意識のうちに自らのコミュニティの文化や価値観のレンズを通して立ち上がる「世界」を生きている。AIなどのテクノロジーが進化する一方で、気候変動からパンデミック、対立や紛争まで、さまざまな問題が複雑に絡み合う現代。もし自分の正しさが、別の正しさをおざなりにしているとしたら。よりよい未来のための営みが、未来を奪っているとしたら。そんな問いを探求するなかでIDEAS FOR GOODが辿り着いたのが、「多元世界(プルリバース)」の概念だ。本特集では、人間と非人間や、自然と文化、西洋と非西洋といった二元論を前提とする世界とは異なる世界のありかたを取り上げていく。これは、私たちが生きる世界と出会い直す営みでもある。自然、文化、科学。私たちを取り巻くあらゆる存在への敬意とともに。多元世界への旅へと、いざ出かけよう。
IDEAS FOR GOODでは、2023年6月に「多元世界をめぐる(Discover the Pluriverse)」という特集を始めた。これまでトランジションデザイン、脱植民地化、ケア、フェミニズム、脱成長などのトピックを扱ってきたが、それぞれの深淵なテーマと向き合うたびにそれらは「では、自分(たち)はどうなのか?」という問いとして跳ね返ってくる。
そんな内省的な態度で、一度ジャーナリズムについて考えてみたい──そうした想いを持って、今回編集部は多摩美術大学の教授であり、デザイン人類学者である中村寛さんに話を聞いた。
中村さんは、デザイン人類学と呼ばれる分野で研究をする。デザイン人類学とはその名のとおり、デザインと人類学が交差する学問だ。デザイン人類学は、人類学の手法と理論をデザインの実践に適用することで、人々の生活や文化を深く理解し、その知識をもとに製品やサービスのデザインを行うことを目的とする。このアプローチは、単に機能的なデザインだけでなく、文化的、社会的な文脈に根ざしたデザインを生み出すことができるため、多くの企業や組織からも注目されている。
そもそも人類学は、ビジネスに生かされるのか。世の中を良くするメディアの役割、そして、「書く」ことの危うさとは。日頃積み重なっていた疑問を、中村さんに率直にぶつけ、ディスカッションの時間を持った。本記事ではその記録を残していきたい。
話者プロフィール:中村寛(なかむら・ゆたか)
 文化人類学者。デザイン人類学者。物書き。アトリエ・アンソロポロジー合同会社(Atelier Anthropology LLC.)代表。多摩美術大学リベラルアーツセンター/大学院教授。KESIKI Inc. Insight Design担当。
文化人類学者。デザイン人類学者。物書き。アトリエ・アンソロポロジー合同会社(Atelier Anthropology LLC.)代表。多摩美術大学リベラルアーツセンター/大学院教授。KESIKI Inc. Insight Design担当。
人類学者が在籍している企業も?人類学とビジネスが出会うとき
Q. まず、中村さんの普段のお仕事や研究領域について教えてください。
多摩美術大学美術学部リベラルアーツセンター/大学院で教鞭をとっています。また、2022年7月にはアトリエ・アンソロポロジー(Atelier Anthropology LLC.)という会社を立ち上げ、さらにカルチャーデザインファームである株式会社KESIKIでも活動しているので、今は3つほど仕事を掛け持ちしていることになります。
研究に関していうと、今までアメリカを中心としたフィールドで、人類学の研究をしてきました。テリー・ウィリアムズの書籍『アップタウン・キッズ―ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』を翻訳したり、学生たちと『Lost & Found』という冊子や、『はじめのはなし』という絵本を作ったり、博士論文の日本語訳である『残響のハーレム──ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015)という書籍を執筆したりしました。最新の仕事としては、写真家の友人とアメリカじゅうを旅して記録した『アメリカの〈周縁〉をあるく──旅する人類学』(平凡社、2021)があります。
このように、今までは、フィールドワークに基づいてエスノグラフィーを書く仕事がメインでした。人類学は基本的に対象への「介入」を避けるので、できることは記録を残し、エスノグラフィーを書くことであり、たとえ問題があってもその場に介入し、影響を与えることはできません。しかし、私としてはエスノグラフィーを書くだけにとどまらず、問題にアプローチしたいと考えるようになりました。そして、7年前から「社会実装」までおこなうアカデミックモデルをつくりたいなと思うようになり、「デザイン人類学」という分野に出会いました。
デザイン人類学は、新しい製品・サービス・慣習行動・カルチャー・社会関係などをリサーチに基づき着想、結晶化、開発、実装する応用人類学の一種です。その過程でエスノグラフィーの方法が用いられることもあります。特定のフィールドで見たり、聞き取ったりしたことを、具体的なデザインに活かしていきます。
デザインの分野に関わってからは、若くて熱量のあるデザイナーと一緒に話をする機会が多くなりました。彼らは、デザイン概念を広く捉えなおし、例えば地域に深く関わることもあります。写真を用いたり、フィールドワークをおこなっていたりと、共通する部分も多い一方で、違いもたくさんあり、一緒にできることが随分あるなと思うようになりました。今は企業と一緒に佐渡島や旭川の地域プロジェクトにも関わっています。こう考えると、もはや「研究」というよりは、「実装」と「デザイン」のプロジェクトですね。
Q. 中村さんの活動では、研究から一歩進んで社会実装まで行われているのですね。アカデミックな領域と実践の境界を定めず、あえて曖昧にしながら活動されているのが印象的です。企業の方と協業するようになったのは、積極的な働きかけによるものでしたか、それとも自然な成り行きだったのでしょうか?
出会うべくして出会った感じもありますし、積極的に出会いにいったものもあります。
経済学や政治学などはその限りではないでしょうが、人文社会科学系の学問分野の多くは、ビジネスのことはあまり考えてこなかったですよね。もっと言うと、批判社会学とか批判人類学などの批判理論に関わる人々は、どちらかというと反商業主義だったと思います。
一方で、フィールドワークをする中で出会ったものをしっかり見つめ直していくと、当たり前なんですが、経済活動は非常に重要だということがわかります。商業主義自体が変わっていかなければいけないことは間違いないのですが、それはアカデミックな分野が経済活動を研究対象として扱わない理由にはなりません。自分でビジネスをやりはじめてから、経済活動に関して見過ごしていたことは多いなと思いました。
とはいえ、もちろん、人類学と企業の連携は新しいものではありません。1970年代・80年代には、特に欧米で、人類学の専門家が企業で働いたり、場合によってはチームを率いてUXデザインを手掛けたり……というということがより一般的になりました。そのように人類学のバックグラウンドを持つ人が企業やパブリックセクターなどでも活躍できる状況は健全ですし、日本でそうした共同作業ができていないのは、非常にもったいないなと思っていました。
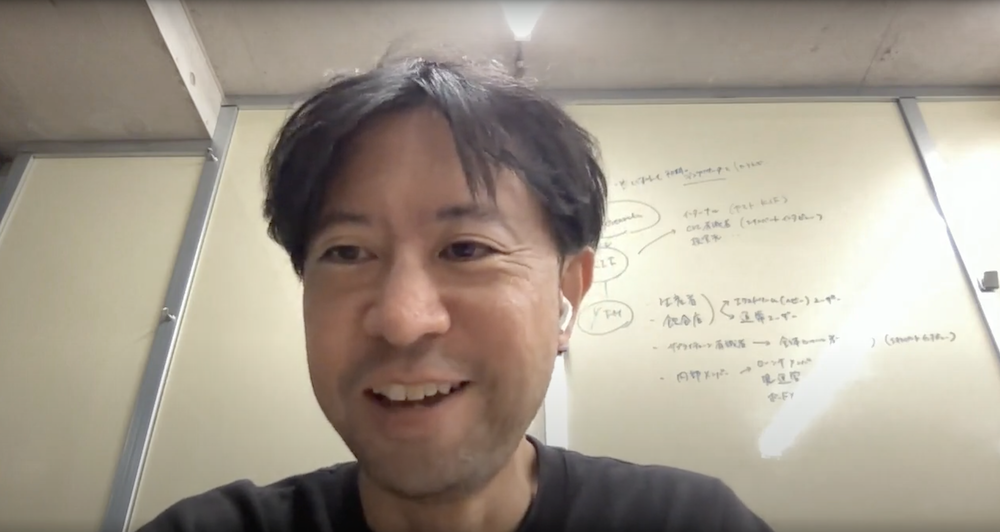
インタビュー中の様子
不満を言っているだけでは変わらないので、自分で会社を立ち上げました。そうすると、思わぬ出会いがたくさんあったのです。
日本にもソーシャルグッドに向けて真剣にビジネスに取り組んでいる人たちが多くいます。しかも、何かを変えるために革命を叫び、一気に変革を起こすのではなく、「気がつかないうちにどんどん変わっていく」ような仕組みづくりをしているデザイナーが多いことにも気付きました。そうしたコミュニティに対して、アカデミアの視点から働きかけ、一緒にムーブメントを起こすこともできるのではないかと思ったんです。
Q. 企業と協働するインパクトはすごく大きいですよね。企業が何か新しいことを取り入れるとなると、数量的なもの、つまり経済性が大事になると思うのですが、そのあたりはどのようにコミュニケーションを取られているでしょうか?
今もまだチャレンジの途中なのですが、一つはデザイン人類学が入ることによって生まれるビジネスへのインパクトを、もう少し上手な形で見せられないかなと思っています。
人類学の視点をビジネスに取り入れるため、同じ時期にメッシュワークという会社を立ち上げた比嘉夏子さんと話をしているときに、彼女が教えてくれたことがあります。欧米圏で人類学者を採用している会社の話を聞いていると、彼らは、「すでに人類学がビジネスにとって目に見えて明らかな効果を与えることは知っている」と言うそうなんです。だから、「人類学のビジネスへの有効性なんて改めて証明する必要などない」と。
しかし、日本では人類学とビジネスの関係性はほとんど知られていない。むしろ、マイナスイメージからスタートすることのほうが多いかもしれませんね。これには、日本では多様性をめぐる議論がなかなか進んでいないこととも関係しているかもしれません。人類学は、「人間」というものの多様性と普遍性とに向き合い続けてきた学問ですので、異質な者同士でコミュニケーションしながらも社会をつくろうとしたり、商品やサービスを提供しようとしたりする社会では、否応なく求められるのですが……。いずれにせよ、だからこそ、デザイン人類学が与えるソーシャルインパクトについて、きちんと「見える化」することが必要だと思っています。
そしてその際には、定量化モデルだけに依存するのではなく、「地域の人の表情の変化」「暮らしがどのように豊かになったか」など、質的なことがらを損なわないように、いろいろな形でインパクトを見せるのも大切だと思います。それらのインパクトを一枚の絵や写真で表現し、わかりやすく表現することが必要なのではないかと思っています。
また、人類学とビジネスの多様な関係を実践しながら示していくこと、それによって、ちゃんと社会・経済的インパクトを生んでいくことも大事だろうと思います。巨額の売上をあげる会社とソーシャルグッドを一緒につくることもできるだろうし、赤字にならないくらいの規模で適正に稼ぎながらソーシャルな事業を展開する会社に伴走することもできるでしょう。経営者のかたわらに、ビジネスリーダーのかたわらに、人類学者がいることで、変化の多い今のような時代に、さまざまなかたちでのビジネス戦略が可能になるはずです。
人類学とジャーナリズム。私たちの中の「権力」にどう向き合うか?
Q. ここからは、「人類学と企業の協働」というテーマのなかでも、人類学とメディアの関係について焦点を当てていきたいと思います。人類学の視点がメディアやジャーナリズムに応用されることもありうるのではないかと考えているのですが、中村さんがジャーナリズムに期待することはあるでしょうか。
ジャーナリズムの一般的な傾向として「日々の出来事を逐一拾わなきゃいけない」「事件になったもの、巷で話題になっているものに特化して記事にしなければいけない」「多くの人に読まれるようなキャッチーなタイトルや売れるような見出しをつけなければいけない」など、学問とは異なる様々なモチベーションがあると思います。
ですが、私個人がジャーナリズムに期待していることは、日々の出来事をさらうのではなく、一つの事象をじっくりと読み解き記事にするような書き方です。たくさんのニュース記事をひっきりなしに出し続けるのではなく、「特集」を作っていくイメージでしょうか。
しばらく前に『ニュース・ダイエット』という本が流行ったのをご存知でしょうか。この本自体には賛否があるのですが、その中で、かつて一日のほとんどをニュースチェックに費やしていた著者が、一切ニュースを見ない期間を設けてみた、というエピソードが出てきます。

Image via Shutterstock
その結果、何が起きたか。「何の問題もなかった」と著者は言うのです。むしろ心が穏やかになって、書物を読んだり考えたりする時間が増え、物の本質がちゃんと見えるようになったと。メディアが「爆弾事件がありました」「テロがありました」と報じれば報じるほど注目が集まり、読者・視聴者の危機意識が高まります。そしてそれこそ、テロリストの思うつぼなのだと著者は語ります。
出来事が起こったときにすぐにそれを報じる記事に対し、特集記事のように、長い時間をかけてその出来事の裏にあるものを読み解いていくというやり方は、実は人類学の仕事に近いように思います。良質な特集記事は、まるで短いエスノグラフィーのようだと感じることもあります。そうしたものがジャーナリストから出てくると感動しますし、実際そうしたジャーナリストの仕事から私は強い影響を受けてきました。もしかすると、エスノグラフィー以上にノンフィクションや記録文学などのほうをよく読んだ気もします。ですので、今後も期待していることです。
もう少し言うと、ジャーナリストも、人類学者や社会学者も、単著で記事や本を書くという幻想から自由になったほうがいいとも思います。ジャーナリストが人類学者と一緒に特集記事を書いたり、さまざまな発信の方法を模索して試したり、ということが、もっとごく普通におこなわれるようになったら良いですよね。ジャーナリストと人類学者では、おそらく関心が一緒でも、得意なことが違ったり、目の付けどころが違ったりするわけですから、協業の可能性は大いにあるはずです。
Q. ジャーナリストは記事を書く仕事、そして人類学者もエスノグラフィーなどの「記述」を伴う仕事です。どこの国で書かれた文献やサイトを参照するか、どの言語で発信するか、誰に話を聞くかなど、書く仕事も色々な権力関係の中で成り立っていると思います。中村さんが「書く仕事」にまつわる権力関係に関して、感じている課題はありますか?
やはり言語の問題は大きいですよね。水村美苗さんの『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で』(ちくま文庫、2015)という本にも出てくるテーマですが、土着のものが失われていく感覚は、日本における「カタカナ語」について考えるとよくわかると思います。たとえば、日本語圏で生まれ育って教育を受けた20〜40代の世代が、60年前に書かれた土着的なものに関する文章に登場する単語がわからず、逆にカタカナの概念的なものの方がよくわかる、ということが起きますよね。
私自身もそうです。でも、私はこれって結構怖いことだなとも思います。カタカナ語を使うということはつまり、ほとんどの場合、英語圏で出来上がった概念を使って、自分たちの身のまわりの問題を読み解き、英語圏で出来上がった救済策を使って、自分たちの状況を解決するということです。ここに見えにくい権力関係が生まれるのです。
例えば「ハラスメント」も「フェミニズム」もすべて英語圏から入ってきた概念です。自分たちの心身が経験する「痛み」を理解して、語るためには、英語圏の概念を経由しないといけなくて、そうした「痛み」の救済方法も、英語圏の概念や物語が用意してくれている。
誤解がないように念のために書いておくと、輸入概念だからだめだと言っているわけではありません。そうではなく、言葉を扱う以上、言葉や翻訳が内包する権力関係には注意を払う必要があると言っているだけです(そうしないと、たとえば、「痛苦」の感じ方や、その救済方法まで、「グローバル・スタンダード」という名の「西洋中心スタンダード」に則って、あまり幸福とは言えない競争をしなくてはいけなくなってしまいます)。
権力は、こういう非常に身近なところにあるのにもかかわらず、私たちは小学校の段階から権力のことを教わらないで育ちます。今お話したような、権力の不均衡の問題に意識を行き渡らせるには、権力の働きに非常に敏感じゃないとできないし、ある種の訓練が必要です。そういう点でも、デザインの力が活かせると思っています。
相手と会話し、それを書くときの心得
Q. ジャーナリストのインタビューや人類学者のフィールドワークでは人の話を「聞く」作業が発生します。相手の話を聴く上で、中村さんが気を付けていることはありますか?
私が気をつけていることは、状況を読みながら、心身をひらいて「会話」をするという「かまえ」です。
話しながら湧いてくるような疑問や、あんまりその時点までは考えてなかったような質問もぶつけていくし、こっちも逆に自分自身を晒すように心がけています。話題がシリアスなものになればなるほど、「私はこういうふうに考えている」「ここが一番葛藤している部分だ」「こんな恥ずかしいミスがあった」などをすべて話し、自分自身の「鎧」を脱いで、「裸状態」になった上で、「会話」することを意識するようにしています。
また、相手の答えや語りに対してさらに応答する場面があると思うのですが、相手の意見を「定量データ」のように扱わないようにも気を付けています。聞くことができた、その人なりの答えなり語りなりを「量化」したり、「デジタル」に処理したりしてしまったら、非常にもったいない。定量データの分析からもわかることは山程ありますが、フィールドでは出会うことがらの「質」を、なるべくなにごとかに還元せずに呑み込む。たとえば極めて私的な語りが返ってきたとしたらその回答をそのまま減じないように受け止め、その背後にあるものを、どんなふうに解釈できるかを考えるようにしています。
具体的に取り組める思考のツールとしては、二つのものを比較する際に、「異なっている」と言われるものの間に共通性を見つけてみる、「同じである」と言われているものの間に差異を読み解く、といったものがあります。そのようなトレーニングも大事です。

Image via Shutterstock
また、相手の回答を「質的」に捉えることに関連して、彼らの言葉をエスノグラフィーに記載しながら解釈する際は、なるべく余白を残すような書き方を心がけています。
「この人はこう言った」という書き方は、理解にもつながりますが、ステレオタイプにもつながりやすいですよね。例えば「アフリカ系アメリカ人の40代男性がこう言っている」と記載した場合、読み手は「彼は『アフリカ系の人だから』そう思ったのか」「『40代だから』そういう行動をしたのか」と捉えてしまい、それがステレオタイプを補強することも多くあります。このように「〇〇は△△である」と切り分けることによって理解するのも、一つの学習のプロセスではあるのですが、それだけだと書籍もエスノグラフィーも非常につまらないものになると思います。
私の場合、書物を読む際の喜びは、解説的な文章を読んで何かを理解すること以上に、思いもよらない想像が膨らんだり、ものの見方を変えられたり、といったことにあります。だからこそ、自分が文章を書くときも、読者が「もしかしたらこうなんじゃないかな」という想像を働かせられる、「余白」や「含み」のある表現や言葉を使うように心がけています。
実際、言葉を発する人もその「含み」の中で生きています。私たちも日常会話で、言葉の意味を100%わかって使うことは、ほとんどありませんよね。どんなに近しい恋人でも、どんなに仲の良い親友でも、あるいはどんな家族でも、ディスコミュニケーションがあって、「正確に」発話行為がなされないことや、「正しく」理解されないことが起こります。そのとき、相手を断定しない(アイデンティファイしない)態度が大事になってくると思うのです。誤解が新たな発想を生んだり、ディスコミュニケーションが関係を育んだりすることがあるのですから。
編集後記
メディアとしての役割は単に情報を伝えるだけではなく、常に情報を切り取る責任がついてまわる。それは、「どの情報を掲載するか」ということはもちろんのこと、「どの情報を掲載しないのか」ということに対してもだ。
「書く」仕事に携わる人は、その中立性を担保するために、冷静でいなければならない一方で、本当に伝えたい情報を発信するにはぐっと現場に入り込まなければいけない。そして、そこで織りなされる会話に主体的に参加することで、はじめて現場のことが少しだけわかってくる。その参加の過程に、躊躇はいらないのかもしれない──今回中村さんから人類学の視点を得て学んだことは、ジャーナリズムだけではなく、新しいサービスやシステム、そして言説を生み出すビジネス全体への示唆があることのように感じた。
そして、現場に入り込み、そこで得た体験をもとに新しい事業やデザインを生み出そうとするとき、アカデミアの人に力を借りたり、異業種の人と協働したりすることもできるのだ。そうして生まれるもしれない新しい発想に、心が踊った取材だった。
【参照サイト】株式会社KESIKI
【関連記事】人間社会の「当たり前」を解体する、芸術人類学【多元世界をめぐる】



























