特集「多元世界をめぐる(Discover the Pluriverse)」
私たちは、無意識のうちに自らのコミュニティの文化や価値観のレンズを通して立ち上がる「世界」を生きている。AIなどのテクノロジーが進化する一方で、気候変動からパンデミック、対立や紛争まで、さまざまな問題が複雑に絡み合う現代。もし自分の正しさが、別の正しさをおざなりにしているとしたら。よりよい未来のための営みが、未来を奪っているとしたら。そんな問いを探求するなかでIDEAS FOR GOODが辿り着いたのが、「多元世界(プルリバース)」の概念だ。本特集では、人間と非人間や、自然と文化、西洋と非西洋といった二元論を前提とする世界とは異なる世界のありかたを取り上げていく。これは、私たちが生きる世界と出会い直す営みでもある。自然、文化、科学。私たちを取り巻くあらゆる存在への敬意とともに。多元世界への旅へと、いざ出かけよう。
人類学とは従来、「ヒト」を研究する学問を指す。生物としての遺伝子や他の種との違いをめぐる科学から、集団での文化、民俗、宗教、社会制度まで。幅広く探究し、記述・考察していくのが一般的だ。
今回はそんな人類学に、アートの要素を組み合わせて研究する人の世界を垣間見ていく。秋田公立美術大学で「芸術人類学」を教える、石倉敏明さんだ。石倉さんはもともと、ヒマラヤ山麓の少数民族の神話を研究しており、日本では東北地方の山に入って伝統的な山の思想を学んでいた人だ。2005年からは多摩美術大学で「芸術人類学研究所」の設立にも関わった、人類学とアートをつなぐ媒介者の一人である。
現在は秋田を拠点として、さまざまな専門性を持ったアーティストとの共同制作や展覧会企画なども行う石倉さん。代表作は、日本の美術家・作曲家・建築家と協働した「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」だ。人間と自然の関係を問う作品として、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館で展示された。

写真提供:石倉敏明
今回はそんな石倉さんに、なぜ人類学とアートを組み合わせたのかを問うてみた。回答を深掘りしてみると、現代を生きる私たちが問い直すべき大切な学びを得ることができた。その一部始終をお届けする。
話者プロフィール:石倉敏明(いしくら・としあき)
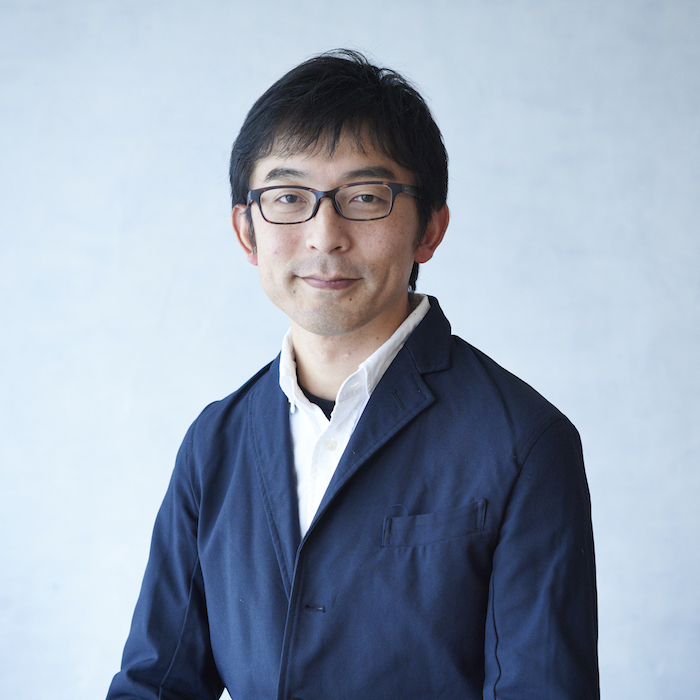 1974年東京生まれ。芸術人類学者。秋田公立美術大学准教授。シッキム、ダージリン、ネパール、東北日本等でフィールド調査を行い、環太平洋の比較神話学やアーティストとの共同制作をおこなう。2019年、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」に参加。共著書に『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』『Lexicon 現代人類学』『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』など。
1974年東京生まれ。芸術人類学者。秋田公立美術大学准教授。シッキム、ダージリン、ネパール、東北日本等でフィールド調査を行い、環太平洋の比較神話学やアーティストとの共同制作をおこなう。2019年、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」に参加。共著書に『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』『Lexicon 現代人類学』『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』など。
なぜ、芸術と人類学なのか
Q. まず、石倉さんの経歴がとても面白いと感じました。もともと神話学を学んでいたところから、どのように芸術人類学にたどり着いたのですか?
油彩画家で小学校の図画工作教師だった母の影響でもともとアートには関心があったのですが、中学校以来の美術教育に反発して、実は20代後半までは特に現代アートに対するアレルギーがありました。美術館よりも、博物館や世界中の聖地に関心があり、世界中の音楽の多様性にも惹かれていました。そんな理由もあって大学院では中沢新一先生のゼミでアジアや日本の神話研究に没頭しており、物語の背後にある絵画イメージや遺跡の建築、音楽や芸能、仏教やヒンドゥー教の仏像・神像にはいつも魅了されてきました。
そんなときに、偶然、最初の就職先となった多摩美術大学芸術人類学研究所で、とても魅力的なアーティストや音楽家、工芸作家と出会い、芸術人類学の扉が開かれたのです。所長の中沢先生をはじめ、所員だった鶴岡真弓さん、港千尋さん、長谷川祐子さん、椹木野衣さんや若手の研究者たちの影響で、旧石器時代の洞窟芸術から同時代の実験的で多感覚的なアートまで、世界中の多種多様な芸術に関心を持つようになりました。特に、音楽家であり映像作家の高木正勝さんとの出会いが強烈でした。彼と出会っていなかったら、僕は芸術人類学の道に進んでいなかったかもしれません。
Q. なぜ「人類学」と「アート」を組み合わせることになったのですか?
20世紀から21世紀にかけての転換期に、人類学の世界とアートの世界に、共通の課題が見えてきたんです。これまでの文化人類学では、色々な文化の多様性や少数民族の存在を認めながらも、あくまで「人類」という種に特有の現実をとらえようとしてきたし、その人類が生きている世界のことを中心に考察を進めてきました。
そこで当時生まれた疑問が「僕たちがいま生きている単一の世界だけを正当なリアリティだとする姿勢は、本当に妥当なのだろうか」というものです。動物や植物、昆虫、微生物、その他の無機物といった人間以外の世界のことを考えなければ、人類学も先に進めないような状況が訪れていました。

同じ時期に、アートの分野でも「人間中心主義」が疑問視されていました。アートとは作者が中心にいて、その周りにある美しいものを見たり感じたりして作品制作をするのが一般的でしたが、人間が一方的に、ランドスケープや動植物、そして他の人間たちを対象化したり資源化したりするだけで良いのか、という疑問ですね。また、アーティストたちのなかに本格的な調査活動をもとにした作品制作を行う潮流が生まれ、さまざまな学問との接点が生まれてきました。
そこで、似たような問いを持った人類学とアートの分野で、いよいよ共同実験をしようという動きが21世紀のはじまりに起こったんです。20世紀の学問が作り上げてきた「人間とは何か」という問いを根本から問い直す機運が高まってきた時期で、多摩美大に「芸術人類学研究所」が立ち上がったのも、まさにこうしたタイミングでした。
Q. 芸術人類学とは、どのような学問なのでしょうか?
芸術人類学とは、人類学の視点でみると、「人間はなぜアートを通して世界と関係を結んでいるのか」「そもそもアートとは何か」「実際にどうやってアートを生み出しているのか」を問い直す学問だといえます。逆にアートの視点でみると、「アート=美しいものを作るという美学的な限界を超えて、どうしたら多様化した表現のフィールドを拡張できるか」「芸術の普遍性とは何か」を問い直す学問といえそうです。
また、他の芸術分野と違う点として、芸術人類学はアートという活動を閉ざされた専門領域と考えるのではなく、現生人類の多様な創造性と広く結びつける特徴があります。例えば近現代の美術を研究すると、どうしてもヨーロッパのルネサンス時代に制度化された作品作りのフォーマットに辿り着くのですが、芸術人類学ではアートの起源がヨーロッパにあるという前提そのものを疑い、世界各地に異なる源泉が存在することを探ろうとしています。
Q. 「ルネサンス時代の作品作りのフォーマット」について、詳しく教えてください。
「自然と人間を切り離し、自然界に資源・資材と美の源泉を見出そうとする」近代的なアートの起源は、ヨーロッパの歴史そのものにあります。
ユダヤ・キリスト教の一神教的な背景を持った「超越的なもの」への憧れと、ギリシア・ローマ世界の豊かな多神教的神話の緊張関係のなかで、僕たちが美術館で目にする大理石彫刻や宗教絵画が生まれました。その背景には、人間を世界から分離して超越化しようとするキリスト教の世界観と、自然を分類して抽象化しようとするギリシアの学問が大きな影響力を持ってきたのです。
そして、そうした神話や宗教の背景を乗り越えようという意識を持ったポスト・ルネサンス期のアーティストたちが、はじめて自身の目の前にあるモノ、景観、人間たちを審美的な対象として描き出す絵画や彫刻の運動をはじめました。18世紀以後のヨーロッパで発達した視覚芸術は、ユダヤ・キリスト教の一神教的な神話と、ギリシア・ローマ的な多神教の神話を乗り越えようとする、新しい人間主義の運動と切り離すことができないのです。
ところが20世紀後半になると、世界中に非ヨーロッパ的なアートの源流が発見されるようになりました。21世紀の現在では、世界の歴史の中に再びアートの可能性を見出そうとする潮流が大きくなっています。近現代の美術制度を乗り越えようとする新しいアートの実践は、ヨーロッパ社会によってもたらされたグローバル資本主義や人間中心主義を乗り越えようとするエコロジーの思想とも、深く結びついています。
Q. そんな世界の潮流のなかで、良いと思ったアートの事例はありますか?
人類学的に拡張された意味での「アート」の実例は、世界中にたくさん存在しています。例えばインドのメガラヤ州にある「生きている根の橋(Living root bridge)」は、その地に住むカーシ族とジャインティア族の人たちが長い時間をかけて作り上げた「生きているアート」であり、「異種共生のデザイン」の実例です。
急流の川を渡るために、コンクリートや木材を使うのではなく、生きたゴムの木の力を借りて、少しずつ対岸に伸ばしていったことで、人が通れるくらいの丈夫な橋になったのです。今では観光地にもなっていますね。

インドにある「生きている根の橋(Living root bridge)」 Image via Talukdar David / Shutterstock.com
この橋は、その地域に暮らす人たちが必要に応じて作っていったインフラです。個人のアーティストが傑作を作って展示会を開いたりするわけではなく、生活者が少しずつ作っていく「生活の中の美」があると言えます。
また、人間が助かるだけでなくゴムの木も生きながらえるような設計になっており、親から子へと世代を超えて作られた橋であるということで、使えるようになるまで40年、そこから今後200年続く橋だと言われています。まさに、「人間がいま生きる世界」を超えた新しいリアリティを作るような取り組みだといえます。
現在、六本木の21_21 DESIGN SIGHTで開催している展覧会「Material, or」では、写真家のピート・オックスフォードによるこの橋の写真作品を展示しています。人類学は基本的に、論文を読んだりデータを実証したり、また論文を書いたりといった「論理的な言語が優先される世界」なのですが、そこにこの事例のような、アートという別の感性に訴えかける方法が加われば、人類学のフィールドもより広がるのではないかと僕は考えています。
言語が優先されるこの世界で、「別の感性」を考える
Q. 「論理的な言語が優先される世界」の課題について、詳しく教えてください。
大学の研究者が活動するアカデミックな世界では、一般的に、文章を書くことが標準的なアウトプットとなります。人類学の分野に限らないと思うのですが、専門的な研究をしていると、どんどんマニアックになっていき、同業者しか読まないような論文がたくさん書かれます。もちろん確実で高度な専門性という視点から、そのように細分化された論点を積み重ねていくことは、とても重要です。しかし、それは、その分野を知らない一般の人にとっては非常に難易度が高く、アクセスしにくい情報なのです。
「科学の知識」はとても重要で、人類全体の遺産と言ってもいいほどです。ですが実はそれと同じくらい重要なのが、それぞれの地域に継承されている「在来の知恵」というものです。それはしばしば「物語の知」として語られる、とイギリスの人類学者ティム・インゴルドが指摘しています。「物語の知」は一見、非論理的で、非科学的で、データで示すことができなくて、時には「非現実的」に思えることもあります。こうした知は、科学の影に隠れてしまい、現在はとても見えにくいものです。
そういった知恵こそ謙虚に学んだほうがいいという姿勢のもと、昨今の人類学者は世界各地にフィールドワークに出かけています。
Q. そういった非科学的なことが現代社会で評価されなくなったのは、なぜでしょうか?
要因の一つとしては、社会のなかでいくつかの単純化が行われていることだと考えます。たとえば、人類にとって「経済発展こそが目指すべき道である」という思想の単純化ですね。人々が同じ尺度・イデオロギーを持って効率よく物事を進めていくことで、経済は発展していきます。その一方で、土地に根付いた、限られた資源で豊かに暮らすための知恵は「用無し」になりつつあります。
例えば、古来日本でもお米を取った後に残る「稲わら」で草履やしめ縄といった「わら細工」を作る技術が伝承されてきました。秋田では「カシマサマ」という巨大な人形道祖神を、「稲わら」で作っています。かつては住宅の屋根も茅葺が主流でしたし、身近な山で採れる植物の特性を活用して籠などの道具を作り、生活空間を設計してきました。しかし大工さんに頼んで数千万円で建売の住宅ができる時代が訪れると、そういった知恵は徐々に使われなくなっていきました。道具も、今ではプラスチックなどの石油由来の素材で大量生産されて、身近な素材で自作する技術は失われる一方です。
このように身近な環境由来の素材を使わなくなった近代の特性として、「人間」と「自然」をはっきり分けていく動きがあります。現在、都市部に住む人にとって「自然」はあくまで週末に訪れるような癒しの対象となっており、普段の生活の外にある存在だとされていることですね。本来、自然と文化は分ける必要はないのだと思いますが、なぜか「外の存在」とされた途端に、ロマンチックで美しいものだという投影が起こったりもします。
Q. ただ、最近ヨーロッパの国々では人間中心主義を脱しようという動きも出てきていますよね。
はい、彼らは過去の「人間中心主義・理性中心主義・植民地主義」などの歴史を振り返ったうえでこれからどうするかを課題とし、研究を進めているように思えますね。特に近代美術の制度では、これまでは圧倒的に白人男性が中心の世界であり「見る側」「描く側」「支配する側」でした。
そしてアートといえば、白人の有名な男性画家が、異国(大抵はヨーロッパよりも経済的に発展していない場所)のエキゾチックな女性の裸体や風景を描く、といったものも多くありました。

そういった特定の人や他の生物、自然からの搾取を当たり前としてきた思想が、自然と人間の諸問題のすべての根っこにつながっており、今は問い直されようとしているのです。
▶️ ロンドンの大学が「脱植民地化」に動く。その3つの教育改革とは?
日本の場合はどうでしょうか。明治の開国以来、昔から欧米に対する「追いつけ追い越せ」の姿勢があり、むしろそれが西洋的な考えの支配的な部分を内在化してしまう要因にもなっています。
特に日本の美術大学は、例えば「西洋画」と「日本画」という捩れた歴史や制度を内面化したままアートの中心地を大都市圏に設定してしまうような、無意識のバイアスがまだまだ残っています。その矛盾は、ギリシア・ローマ神話やキリスト教神話に因んだ石膏像をデッサンすることで「近代美術」の制度をそのままインストールしようとする欧米追従の姿勢にも表れています。
そういった制度的な構図を更新するためにも、あえて大都市圏ではなく地方都市の秋田で芸術人類学を研究することが大事だと考えています。東京が日本の文化的な中心地であり、田舎が周縁だという考え方も、形は変われどヨーロッパ中心主義と根本的には同じようなものですから。
Q. 地方で研究することで、どのような面白さがあると考えますか?
例えば今、東北の田舎町に住んでいる僕の周りでは、この脱人間中心主義・脱植民地化・脱男性中心主義といったトピックがとても先鋭的な問いとなっています。地方の美大生の方がそういったトピックについて敏感なのは、少し面白いですよね。また、台湾やカナダの先住民や、インド・メキシコ・スウェーデンの美大生との交流など、「トランスローカル(※1)」な動きもアートの分野で生まれています。
※1 ローカルでありながらも、一つの地域の枠に閉じこもらず、新たな視点で資源などの足元を捉え直し、他の地域とも互いに学び合うこと
秋田にいると、おそらく他の地域からは絶対に出てこないだろうな、という才能と出会うことも少なくありません。かつて僕が人類学を教えた学生で、秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻を卒業した永沢碧衣さんの作品も、地域独自の生態系や、そこに根付く知恵を生かしたもので、とてもユニークです。彼女は、熊から取れる素材である熊膠(くまにかわ)を使い、秋田の大きなツキノワグマを描いて「VOCA展2023(※2)」の大賞を受賞しました。
※2 40歳以下の若手作家による、優れた才能を紹介する現代美術展。全国の美術館学芸員、研究者などに推薦を依頼し、その作家が平面作品の新作を出品し、それを評価する。
これは、永沢さんが実際に秋田発祥のマタギ(伝統的な方法を用いて集団で狩猟を行う者)の文化に参加しながら作った作品です。マタギの世界は基本的に男性限定で、女性が狩りをすることはなかなか認められてきませんでした。永沢さんは、それでも例外的に一緒に猟に加わることを許され、さまざまなことを学んでいます。同時に、彼女はマタギ集団とは異なる地元の猟友会で、いわゆる「有害駆除」の対象とされている、里山に降りてきたクマを捕獲し、自分で解体もしています。
要するに、秋田のクマは、文脈次第で山の神様から授かる「神獣」にも、住民を脅かす「害獣」にもなり得ます。彼女はそんな引き裂かれた世界観の中で、自らクマを狩って解体し、皮を剥いだり、他の猟師と一緒に命を頂いたりしながら制作を進めていきました。

永沢碧衣さんの作品『山衣をほどく』(部分)
何気ない日常から、多元的な世界を生きる
Q. 今回の取材を通して、違う世界で生きることへの想像力をもっと持ちたいと思いました。もしこの記事を見ている人が、自分もそういったアプローチをしてみたいと思ったら、何ができるでしょうか。
多元的な世界を生きるということは、必ずしも新しい知識を得ることではなく、自分たちが今生きている世界やその中に生きている多種多様な存在と出会い直すことだと思っています。例えば僕は「共同体」ではなく「共異体」という言葉をよく使っていますが、それはいま生きている皆が同質だという考えを持たず、異なるものが互いの差異を解消しないまま共存していく世界を見ようとしているからなんです。
それを実感するために、例えば発酵食品の蔵元を訪ねて、身近な場所で異なる生物や微生物と共存しながら生きる人びとの活動をフィールドワークしてみても良いかもしれません。秋田では幸い、味噌醤油やお酒の蔵元が多いので、僕もよく麹菌や酵母菌といった微生物の世界を覗かせてもらっています。
▶️ 共異体について、詳しくはこちら:「発酵」と「地熱」の視点から、異なる個人の共生を学ぶ
それに、田畑で農作業を体験してみることもおすすめです。僕は、秋田の田んぼで草取りをしながら自分の体の「内臓」の延長上に、外の世界につながっている「外臓」というものがあるんじゃないかと想像してみたり、料理をしながら自分の体の中に多数の微生物たちが住んでることを想像したり、散歩の経路を変えてみたりしています。ちょっとしたことで、既にある慣れ親しんだ世界をまったく別のリアリティとして受け止めることができます。

Q. そう聞くと、多元世界を生きるのは意外と身近なことに思えてきました。自分でも、この社会の何かに影響できると思えるような。
ティム・インゴルドの著書『ラインズ 線の文化史』では、まさに自分の生きている道や、あらゆる人間が取る行動がやがて「線」になり、新しい世界制作の一部になるといったことが書かれています。新しい世界制作というと大袈裟なように思えますが、それは選挙に立候補したり政治活動をしたりといったことだけでなく、ほんの小さな行動もその一部となります。
例えば、野原を歩けば足跡が残されてやがて道ができ、線を描いたらそれが絵になり作品になるというような。普段意識していない何気ない行動の積み重ねが、すでに新しい世界を作っていると思っています。そういう意味では、田植えのように稲の苗で田んぼに線を描いていくことも、稲わらを使って制作する人形道祖神や虫送りといった民間行事も、立派な世界制作の一部だといえます。宮沢賢治のいう「農民芸術」のように、芸術は職業芸術家の専売特許ではなく、政治も政治家だけの仕事ではないと思います。
ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻(※3)」という概念も、それに似ています。誰もが自らの創造力によって芸術家になりうる、それは美術だけでなく日々の生活を作っていく政治的な力の源泉でもある、という考えですね。『7000本の樫の木』など市民参加型の作品を通して、ボイスも人間が異なる種と共に生きる「共異体」の世界を作り出そうとしていたのだと思っています。
※3 ボイスが使う「芸術」とは、社会的な高い目的に向かって創造性を発揮すること。絵画や建築だけでなく、教育や政治、科学、哲学、経済学といった社会の構造を変えるさまざまな分野も「芸術」とされる。
僕は、アートというものは人類にとって普遍的な次元で、誰もがすでに手を染めている人間的な活動の一部だと思っています。つまり生活を続けることは、すでにアートをしていることと同義だと考えます。多元的な世界を見ていくなかで、また新たに生活を作り、魂を耕していくというか。
生活という言葉には「生きること」と「活かすこと」が含まれますが、それを展開すれば自然と「生きられた世界」や「活かされた世界」が生まれていきます。それは一部のアーティストだけでなく、誰でもできることではないでしょうか。
【参照サイト】企画展「Material, or 」



























