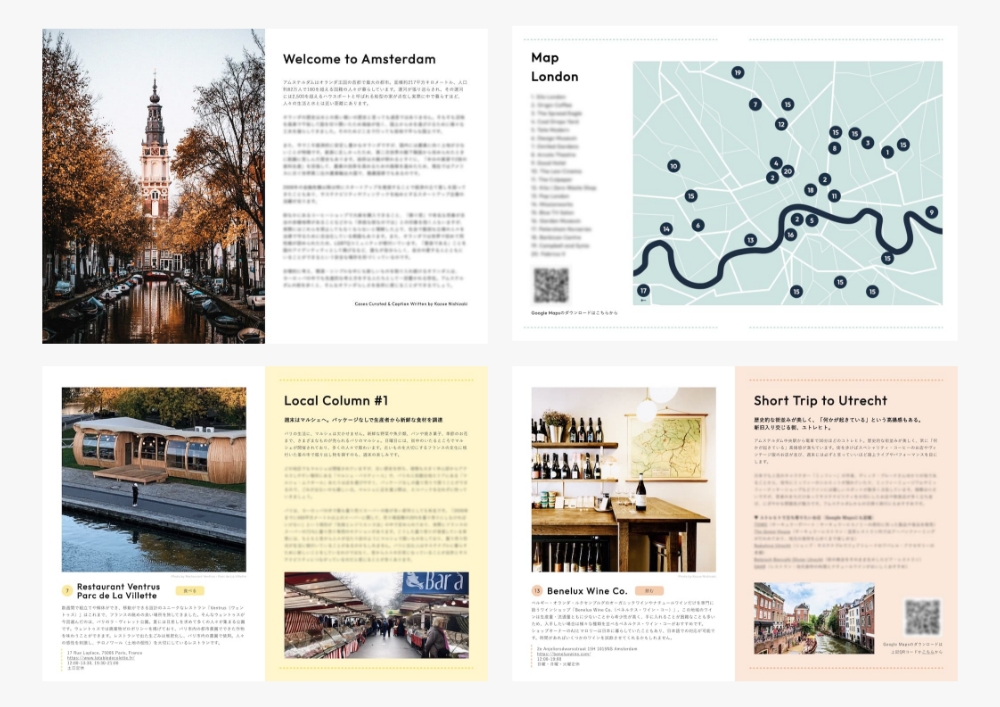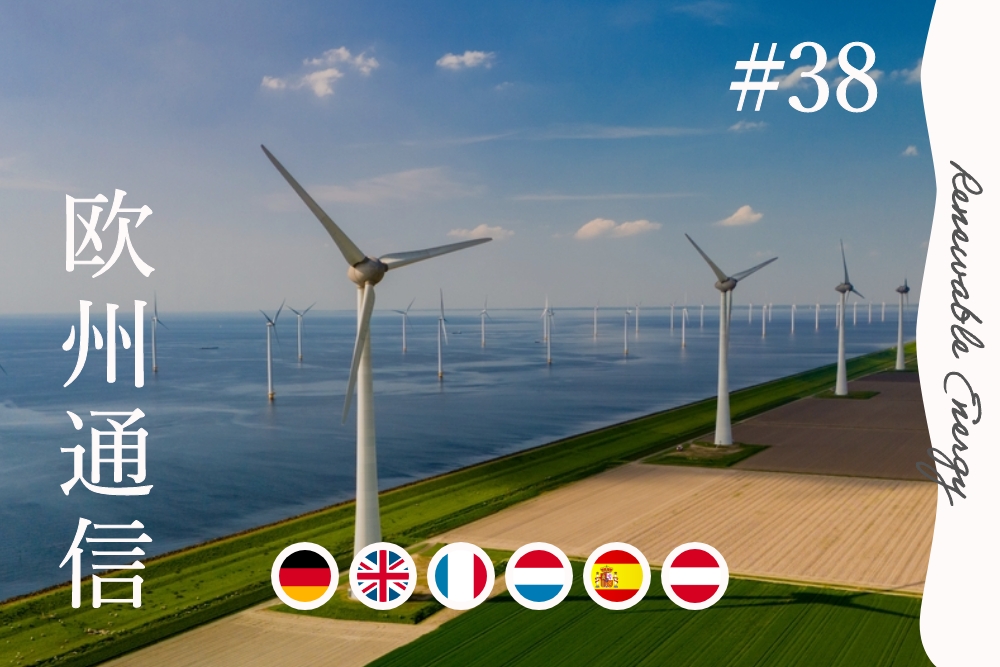近年ヨーロッパは、行政およびビジネスの分野で「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」の実践を目指し、さまざまなユニークな取り組みを生み出してきた。「ハーチ欧州」はそんな欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、日本で暮らす皆さんとともにこれからのサステナビリティの可能性について模索することを目的として活動する。
ハーチ欧州メンバーによる「欧州通信」では、メンバーが欧州の食やファッション、まちづくりなどのさまざまなテーマについてサステナビリティの視点からお届け。現地で話題になっているトピックや、住んでいるからこそわかる現地のリアルを発信していく。
前回は「欧州で注目のサステナブルイベント&カンファレンス」をテーマに、欧州へのサステナビリティ視察・海外出張を検討されている方のために、ドイツ・オランダ・イギリス・フランスでぜひ立ち寄ってもらいたいイベントやカンファレンスを一挙に紹介した。
今回の欧州通信では、「住宅事情(公共・公営住宅政策)」を取り上げる。いま世界的に住宅価格が高騰しており、世界中の200都市のうち、ニューヨーク、トロント、ロンドン、アムステルダム、ソウルなどほぼすべての中心都市の90%は、住むのに手が届かない場所であることがわかっている(※1)。
また、米国の賃貸人のほぼ半数が収入の30%以上を家賃に費やしているという現状もある(※2)。そして人々がそうした生活危機の状況にあることが、さまざまな問題を引き起こしており、住宅価格が10%上昇するごとに、非住宅所有者のメンタルヘルスレベルは7.8%低下することが示されている(3※)。他にも、健康問題や教育水準の低下など、その課題は深刻だ。
今回の欧州通信では、社会的公正の切り口から、各国の住宅に関する取り組みを見ていく。
【オーストリア・ウィーン】借用人がしっかり守られている。「世界で一番住みやすい都市」の賃貸制度
さまざまな調査で頻繁に「世界で一番住みやすい都市」に選ばれる街ウィーン。実際に住んでみて実感するのは、住宅システムが優れていることだ。他の大都市に比べ、ウィーンの賃貸住宅は低家賃で面積も広く内容も充実している。これにはウィーン市による社会的公正に基づく住宅政策が大きく関連しており、その背景には、低家賃は各世帯へ経済的な余裕をもたらし、人々の生活の質の向上につながるとの考えがある。
ウィーン市は、都市計画と規制により住人への合理的な賃貸住宅(ウィーン市内はほとんどが集合住宅)の供給に努めている。都市計画には市が低家賃で提供する公営住宅の拡大政策があり、その成果は、ウィーン市民の約半数が公営住宅や市が何らかの形で介入し補助制度の対象となっている住宅に住んでいることに反映されている。

Image via Wieninfo.com
次に民営賃貸住宅に対する規制だ。個人経営の賃貸については大家が家賃を決定できるが、様々な要件により家賃が高騰しないような制度が設けられている。ウィーンの賃貸に関わる法律は非常に複雑極まるためその内容を全て把握するのは容易ではないと言われているが、概して言えば、そうした複雑で細かい要件によって借用者の権利が強く守られているのだ。
代表的なのが「レント・コントロール」という制度で、家賃価格の決定や引き上げ額において様々な制限が大家へ課せられる。レントコントロールの対象となるのは1945年以前に建設された建物のみだが、実際に制限を受けない賃貸物件は全体の8%以下となっている。このように、ウィーンの包括的な住宅政策と規制が、住みやすい都市としての評価を支えているのである。
【参照サイト】Austrian Landlord and Tenant Act (Österreichisches Mietrechtsgesetz – MRG)
【参照サイト】How Vienna ensures affordable housing for all with an extremely complicated housing system
【参照サイト】Could Vienna’s approach to affordable housing work in California?
【関連記事】もし、街が「女性目線」で作られたら?ジェンダー平等都市・ウィーンを歩く
【ドイツ・ハイデルベルク】地域住民との対話で、国籍・収入・学歴に偏りのない新しい街づくり
ドイツは戦後の経済成長に伴い、1950年代に主に南欧・トルコ・バルカン半島から多くの外国人労働者の受け入れを開始、1990年代にはドイツ人を先祖に持つロシアからの移住者を数多く受け入れた。当時、こうした移民と移民の家族専用に安価な高層団地や戸建住宅が一定地区につくられた。
同政策により、多くの都市では住民の国籍・収入・学歴が偏る地区が形成され、これらの地区の治安は悪化し地価が低下した。現在もこうした地区の多くでは、エリアの評判や子どもの進学状況は向上していない。これを教訓に、現在ハイデルベルク市は再開発地区において、さまざまな収入層の人が住める集合住宅の建設プロジェクトを実施している。
戦後、ハイデルベルク市にはNATOの事務系司令塔が置かれ、家族を含むアメリカ軍関係者は人口の10%を占めていたが、約10年前に世界情勢の変化による軍再編で米軍は完全撤退し、市内中心部近くに広大な敷地が残された。ハイデルベルク市は国内でも地価が高いことから、同地区の再開発について地域住民との協議会を複数回開催し、地価と治安を低下させることなく「誰もが支払える家賃の住宅をつくる」取り組みを展開。米軍が使用していた当時の建物を残しつつそれをアクセントとして改修するとともに、映画館の誘致や緑地形成など、多くの人に魅力的で新旧を交差させた街づくりを進めている。

米軍が使用していた建物(左)と新築住宅(右)をつないだ共同住宅 Photo by Ryoko Krueger
【フランス・パリ】「既存のものを活用」2035年までに手頃な価格の住宅を40%にする計画
フランスでも、住宅価格高騰の危機が例外なく起こっている。慈善団体・アベ・ピエール財団が2024年2月に発表した年次報告書では、パリでホームレスが増加し、公営住宅の申請待ち世帯が2017年の200万世帯から240万世帯に増加していると発表されている。
首都・パリでは、フランス政府が「社会的混在(mixité sociale)」のための政策を推進している。パリは2035年までに手頃な価格の住宅を増やす計画を進行中。この目標を達成するために、オフィスや使われなくなった学校の校舎、ガレージを社会住宅に転換する計画で、市は毎年4,000戸以上の社会住宅と同数の手頃な価格の住宅を用意している。
また、2024年夏に控えたパリオリンピック・パラリンピックに向けて、パリ市は工業地帯を選手村に改造。新しい住宅街は、賃貸住宅、分譲マンション、公営住宅、学生寮、オフィス、そしてカフェやショップなどの用途になるように建設され、オリンピック後には住宅不足緩和につなぐとしている。こうした取り組みにより、現在パリの住民の4分の1が公共住宅に住んでおり、これは1990年代後半の13%から増加している。

パリ13区のオステルリッツ埠頭に位置する公営住宅の開発プロジェクト。iFocus / Image via Shutterstock
この社会的混在政策は、多くの都市で見られる経済的格差を解消することを目指すものだ。このプログラムの恩恵を受けるのは、教師、清掃作業員、看護師、大学生、パン屋、肉屋など。富裕層だけではなく、パリの街を形作るそうした人々を優先的に都市に住まわせることで、多様な街を作り出しているのである。
【参照サイト】How Does Paris Stay Paris? By Pouring Billions Into Public Housing
【参照サイト】‘Adapting the existing’: Paris’ plan to reach 40% affordable housing by 2035
【参照サイト】Projet Fulton à Paris. Logements sociaux, commerces, et cœur paysager de l’île
【オランダ・アムステルダム】投資家らによる居住・商業物件の独占を防ぐ。教師の住宅確保も
欧州他都市に漏れず、オランダも特に都市部で近年住宅不足が深刻である。人口増加に加え、2010年代初頭の市場重視政策による住宅公社株式売却自由化が引き金となり、投資家による住宅取得増加が市場価格の高騰を招き、多くの人が住居を見つけることが困難な状況を生み出した。
昨年公表された調査によると、オランダでは2023年に39万戸の家が不足しており、最近では「住む場所を申請中の学生の平均待機期間が学期よりも長い」というニュースも国内の話題をさらった。実際に、年収が一定基準に満たない人のために低家賃で貸し出す公営住宅入居のための順番待ちはオランダ全国平均で約7年、アムステルダムにおいては18〜19年とも報道されているほどだ。
こうした課題が深刻なアムステルダムにおいて、市は投資家らによる居住・商業物件の独占が課題の大きな原因と認識した上で、街中心において土産物店など観光客だけを顧客とした店の新規開業を禁止、ホテルの新規開業も禁止した。Airbnbなどの民泊については、事前に市に登録をした上で原則最大30泊までの貸出しか認められていない。また、宿泊税も値上げ。現時点で宿泊施設に泊まる際には宿泊者の居住地問わず12.5%の宿泊税がかかる。

Photo by Kozue Nishizaki
さらには近年、高騰する住宅により、教師が市から別の自治体に引っ越してしまったことで市内では教員不足が課題になっている。そのため、教職につく人に賃貸住宅の優先権を与える制度をはじめとする対策に乗り出しており、教師確保と誘致のために2,400万ユーロ(約40億7,000万円)もの予算を投じて取り組んでいる。計画通りに住宅危機緩和策の効果が現れれば、2028年以降住宅難は解消し始めるとの予測がある。
【参照サイト】Waiting lists for student housing longer than a bachelor’s degree takes
【英国・ロンドン】街の風景の一部となった「公共住宅」。ジェントリフィケーションの波に逆らえるか
ロンドンの街を歩いていると、公共住宅(「カウンシル・フラット」と呼ばれる)をよく見かける。1960年代から1980年代にかけて、特にブルータリズムの影響を受けたデザインで建設された住宅群には、もともとは低所得者のほか、失業者、シングル・マザー、生活保護対象者などが優先的に入居できるようになっていた。

Balfron Tower, Image via Shutterstock
カウンシル・フラットは長らく「低所得者」の住居と認識され、社会的な偏見の対象となることも少なくなかったが、時代が変わるにつれて、これらの建築が評価され、ロンドンの持つ一つのカルチャーとして再評価されるようになった。特に著名なブルータリスト建築、例えばBalfron Tower(バルフラム・タワー)などは、文化的遺産としての価値も認められつつある。
しかしながら、このような建築への再評価は、ジェントリフィケーションという新たな問題を引き起こしている。元々は低所得者向けに設計されたこれらのフラットが、中産階級や富裕層によって「再発見」されると、地域の不動産価格が上昇。結果として、元々住んでいた住民が住めなくなるという事態にも陥っている。
ロンドンでは、不動産価格の高騰が続いており、多くの人々が住宅を手に入れることが困難になっている。イギリス国全体あるいはロンドン市で様々な手立てが模索される中、カウンシル・フラットは、本来の目的である「住宅問題の解決」に再び寄与しうるだろうか。
【参照サイト】Council housing
編集後記
世界の不動産市場(商業用・住宅用不動産および農地を含む)は、379.7兆ドルの資産を持つ世界最大の富の源であるが、その多くは世界の上位1%が所有している。ジェントリフィケーションは今回取り上げた都市に関わらず世界中のあらゆる都市で起きている。
そして住宅危機を取り巻く課題は一つではない。生物多様性の危機を、単に木を植えるだけで解決できないのと同様に、格差の拡大やホームレスの人々の増加、権力の集中などの課題を、税制や規制などを微調整するだけでは解決には至らない。また、人々に住まいを提供する必要性こそが、さらに多くの炭素排出や生物多様性の損失を引き起こしていることも確かだ。
スペインのバルセロナなどの都市は、同様の課題を持つパリやロンドンなどと課題を共有しながら、「住宅は建物だけでなく周囲の環境も含む」という意識のもと、全住宅の1%ほどしかなかった公営住宅を増やし、住民がバルセロナに住み続けられるように取り組んでいる。
すべての人が社会的に安全な生活を送るためには、住宅の供給をただ増やすだけでは住宅価格高騰の問題は解決しない。住宅問題の根深い部分を理解した、多面的で包括的なアプローチがいま求められている。
Written by Yukari Fujiwara, Ryoko Krueger, Erika Tomiyama, Kozue Nishizaki, Megumi,
Presented by ハーチ欧州
ハーチ欧州とは?
ハーチ欧州は、2021年に設立された欧州在住メンバーによる事業組織。イギリス・ロンドン、フランス・パリ、オランダ・アムステルダム、ドイツ・ハイデルベルク、オーストリア・ウィーンを主な拠点としています。ハーチ欧州では、欧州の最先端の情報を居住者の視点から発信し、これからのサステナビリティの可能性について模索することを目的としています。また同時に日本の知見を欧州へ発信し、サステナビリティの文脈で、欧州と日本をつなぐ役割を果たしていきます。
ハーチ欧州の事業内容・詳細はこちら:https://harch.jp/company/harch-europe
お問い合わせはこちら:https://harch.jp/contact
「欧州サステナブル・シティ・ガイドブック」発売中
ハーチ欧州では、アムステルダム・ロンドン・パリの最新サステナブルスポットを紹介する「欧州サステナブル・シティ・ガイドブック」を販売中です。
海外への渡航がしやすくなってきた昨今、欧州への出張や旅行を考えている方も多いのではないでしょうか。せっかく現地に行くなら、話題のサステナブルな施設を直接見てみたい──そう思っている方もいるかもしれません。今回は現地在住のメンバーが厳選した、話題のレストラン・ホテル・百貨店・ミュージアムなどのサステブルスポットを一冊のガイドブックにまとめました。実際に渡航される方の旅行のお供にしていただくのはもちろん、渡航の予定がない方も現地の雰囲気や魅力を存分に感じていただける内容になっています。ご購入・詳細はこちらから!
※1 Housing Affordability in a Global Perspective
※2 NEW REPORT SHOWS RENT IS UNAFFORDABLE FOR HALF OF RENTERS AS COST BURDENS SURGE TO RECORD LEVELS
※3 The Importance of Housing on Mental Health
【参照サイト】How Do Housing Prices Affect Residents’ Health? New Evidence From China
【関連記事】スマートシティ先進都市バルセロナに学ぶ。市民を中心とした都市運営の生態学的アプローチ
【関連記事】住宅開発を推進する市民運動「YIMBY」は、公正なまちづくりを実現するか